|
≪伯国日本移民の草分け≫ 鈴木貞次郎著作 (その5)
|
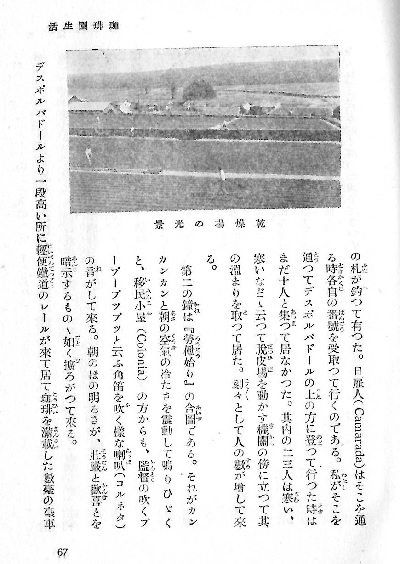 |
≪伯国日本移民の草分け≫(その5)は、水野さんの帰国と一人ぼっちで残された貞次郎青年の珈琲園生活が始まり珈琲園での過酷な毎日の労働が描写される。珈琲園での労働は、収穫は終わり乾燥作業が始まっていた。負けん気で日本移民の見本的な試験期間と捉え頑張るが、1日2食の生活に耐え兼ね4キロ離れた集落にバナナを買いに行く。手持ち金もバナナに化け、奮闘するも器官を痛め病臥するところで終わる。その後は珈琲園生活その九以下に続く。お楽しみに。
写真は、出石さんが送ってくれた乾燥場の光景のページを使用させて貰うことにしました。
|
|
珈琲園生活
一
水野さんたちはとうとう私一人をホテルに残して公使館所在地へ出発してしまった。私は全くの独りぼっちになってしまった。予期したことではあったが、さていよいよ一人になってしまうと、新しい心細さが湧いて来る。言葉もわからない、懐中には大枚五ミルの札がただ一枚あった。勿論私はこの身体以外に頼るべき何物も持っていない。
経験のない珈琲園労働!?!それは私にもある程度の確信がないでもないが、日本移民の見本となって働くと言うことはただ単に労働が出来ると言うだけではすまない。イタリア人がいる。スペイン人いる。ブラジル人もいる。この国際的労働者間に交じって負けてはならないのだ。体力に於いて日本人である私は確かに劣っている。いわんや単なる一学生過ぎなかった私はこの点に於いて彼等と競争して打ち勝ち得る何のプロバビリティがない。私の進むべき道はただ正直に陰日向なく働くことである。今回巡視した結果を総合して見ると珈琲園労働はさほど力を要する仕事でないらしいのが何よりの頼りである。私の責任は重大だ。日本移民契約の能不能はこの小さな肩にかかっている訳だ。どうしても負けてはならない。私はやり遂げて見せる。
こうした子供らしい誇りと自負とは私に少なからず勇ましい念を起こさせた。
× × ×
翌日未明ドクトル・ベント・ブエノ氏の遣わした若者は、グランデ・ホテルの私の部屋をノックした。もう支度の出来ていた私はすぐこの若者と一緒に馬車に乗ってルース停車場に向かった。
もう四月も末である。深い朝霧が細雨の降る様にこめていた。ぼーっと黄色にぼかされた街灯は夢見る様な光景を見せた。カチカチカチと馬の蹄が道路の敷石を打つ堅く冷たい音響がまだ眠っている静かな町の建物に反響して、何となし物語めいた感じを与えた。
切符を買ったり、車室に案内したり、若者は親切に世話してくれた。
発車!
私は窓から顔を出して
「ムイト・オブリガード!」
真実心からこう叫んだ。この若者は私にとってただ一人の肉親のような気がして、じぃっと飽くまでも見入った。徐々としてではあるが汽車の走る速力と、午前五時という早暁の暗さとは、忽ちのうちにこの若者を視界から没してしまった。
「おれはとうとう一人になってしまった!」
こう叫んで窓から身体を引いた時に、気が抜けた様な心細さがあった。
二
言語の通じない私にも、一度旅行した道であるから別に途迷う様なこともなかった。無事にチビリサ駅に着いたのは午後四時半頃であったろう。夕日の満面にさしてる駅前のレールの上には農場のトレンジンニョが着いていた。ワゴン(台車)の上に立って口やかましく指図していた支配人メネゴニ氏は私を見ると飛び降りてきた。
「ボーア・タルデ」
「ボーア・タルデ」
もっと何か言いたかったが、私にはただそれ丈しか解らなかったので、私も簡単に鸚鵡返しに挨拶して手を握り合った。日雇い人達は珍しいものを見物する様に眺めていた。
身軽な支配人はすぐ又台車の上に乗って
「モンタ・モンタ」
それ位な言葉は私にも解った。素早く支配人の後につづいた。私は日雇い人が運んでくれた柳行李やカバンなどを整理してその上に座った。
つい二週間ばかり前に水野さん達と旅行した時は、公使館員、州政府の案内者などと一緒に、お客さん…東洋の珍客…としてこの農場を訪問したのではあった。簡素ではあったが客車も連結されていた。迎えに来た主人ヒルミヤノ・ビント氏の後ろからメネゴニ氏の如きは小さくなっていたのを、ありありと思い浮かべることが出来る。しかるに今や局面が一変して、私は一個の日雇い人として、この農場に来たのである。メネゴニ氏は私を監督する人である。この人の言い付けを守って珈琲園労働を体験しなければならないのが、私の運命である。
「運命!運命!!!どんな運命でも来い!」
心ひそかにこう叫んだ。独りぼっちの私の目にも顔にも無量な感慨が閃いていた。
「Su…Su…Ki…Su…Su…Ki」
メネゴニ氏はこんな風に片言交じりに言って私の顔を見て笑った。
「Suzuki Suzuki」
姓を聞くのであろうと思って私も、力強くはっきりとこう言った。これ以外何も言う事の出来ないおしの様な私の心は悲しかった。
チビリサのコロニヤからは風もない夕空に幾筋となく淡青い煙が悠々と立ち昇って、がたぴしがたぴしと動き出した薪を焚く機関車からはパラパラと火の粉が散った。
三
私に与えられた部屋はグレゴリオと言うイタリア出身の農場書記宅の一室であった。古びてはいたが鉄製の寝台もあった。
蜘蛛の網はすすけた天井を占領し、白く塗った壁は土埃の色に染まって赤くなっていた。床板の下から天井の上へ幾筋もの土の線を引いたものがあった。試みにその土線を払い落とすと、そこから無数の小さな乳白色の虫がぞろぞろ這い出して来た。つぶして見ると一種いやな松脂くさい匂いが鼻をついて来る。話にだけ聞いていた白蟻というのはこれであろうか。好奇心をそそるものはないでもなかったが、自分の住んでいる部屋にこう言う虫が行列をなして往復していると言うことは寧ろ薄気味悪い感じの方が勝っていた。私は、今度は手の届く限り土線を払い落としてしまった。蜂の巣の皮に似てそれよりも、もっともろい土線と一緒に落ちた乳白色の虫の上に私は新聞紙をのせてマッチを擦った。
「火葬だ、火葬だ。」
こんなことをつぶやいて、寂しい心に活気をあおった。灯もない農場最初の夜は、こうした果かないエピソードを残して暮れて行った。
× × ×
翌朝鐘の鳴った時は、もう目が覚めていた。聖市で買った安い木綿服を着ると、すぐ外へ出た。
朝はまだ暗かった。やや霜気を帯びた寒さがひしひしと薄着の身に応えた。明けの明星が燦として東天に光るのは丁度海上から見た燈明台の様に美しい親しみがあった。
乾燥場(Terreiro)には、もうちらちら人の影がして、皆或る方向へ動いて行った。私にはただ乾燥場で働けと言う以外、何の命令もなかったので(その実命令しても理解できなかったろう)黙々としてその後につづいた。他のする通りにすれば間違いなかろうと言う腹であった。珈琲脱皮場(despolpador)に登る石段の前壁に木板が掛けてあって、それに番号を付した円形の真鍮の札が吊ってあった。日雇い人(Camarada)はそこを通る時、各自の番号を受け取って行くのである。私がそこを通ってデスパルパドールの上の方に登って行った時はまだ十人とは集まっていなかった。その内の二、三人は寒い、寒いなどと言って脱皮場を動かす機関の傍に立ってその温まりを取っていた。刻々として人の数が増して来る。
第二の鐘は『労働始まり』の合図である。それがカンカンカンと朝の空気の冷たさを振動して鳴り響くと、移民小屋(Colonia)の方からも、監督の吹くプープープップッと言う角笛を吹く様な喇叭(コルネタ)の音がして来る。朝のほの明るさが、荘厳と歓喜とを暗示するものの如く広がって来る。
デスパルパドールより一段高い所に軽便鉄道のレールが来ていて珈琲を満載した数台の台車があっ働者の朝の仕事始めは、先ずその珈琲を肩に担げてセメントで塗られたタンク(溜め池)に投げ入れるのである。少数の或る者は台車の上に登って他の大多数が肩に珈琲を担ぐ助勢をした。私はその多数の群れに混じって珈琲を肩に載せて運んだ。十数歩の距離に過ぎなかったが、生まれて初めての力仕事、それは想像する様に容易なものではなかった。数台の台車が空になった頃は、私は可成りな疲労を感じた。燃える様に喉の渇きを覚えてデスパルパドール構内にある水管に口を付けた時は息もつかずに水を飲んだ。飲んだ、飲んだ。こんなにうまい水をほしいままに飲んだことを私は過去の記憶に持っていない。
四
乾燥期に於ける聖州の空は、眞に所謂「天高くして秋清し」である。仰げども、仰げども底の知れない碧瑠璃に晴れて片雲の動くを見ない。
朝も七時頃になると日本の桜時を思わせる様な快い寒さである。美しい輝いた太陽の光が乾燥場に流れて露の湿りを拭い去ると日雇い人達は鉄のロード(長さ約一尺五寸、巾五、六寸位のものに長い木の柄を付けている)を取って珈琲をテレーロ(乾燥場)に撒き散らす。馬鹿力を入れずに柄を軽く握った調子でさっさっと散らすと言う様な事は後で覚えたのであるが、私はこの最初の手ならしも不手際ではあったろうが、他の日雇い人達に劣らない丈の仕事をやってのけた。
午前九時に朝飯の鐘が鳴る。何とも言えない嬉しい音である。日雇い人達は何もかも投げ捨てて飯場へ向かってかけて行く。私はアントニオという鼻の赤い痩せた乾燥場監督の宅で飯を食う事になっていたので、皆から五、六分遅れてアントニオに手招きされて一緒に行った。
アントニオはイタリア人で年は二十六、七才位に見えた。マリヤと呼ぶ妻君は美人という程でもないが、如何にもイタリアの百姓の娘らしい顔立ちで赤い縞の着物を着ていた。アントニオよりは五つ位年下らしく、三人の子供の母であった。監督の宅と言うと大きそうに聞こえるが、石灰を塗った壁は赤くよごれて、天井は煙のために思う存分黒く煤けていた。取り柄は板敷を張っている位なもので、少しも移民小屋と変わりがなかった。
朝飯のご馳走に豚油で炊いたご飯(Arroz com gordura)と豆(Eeijao)を煮たもの、それに塩漬けにした豚肉を炒る様に煮付けたのが少々あった。イタリアのお上さんの料理は上品ではなかったが味の付け方がよかった。空腹にはまずいものなしと言う様な意味でなく、実際私は舌つづみを打って食った。自分ながら余りに食うので、幾分控えめにしたがそれでもエスマルタードの皿に三度換えたのを平らげた時、アントニオが言った。
「コメ コメ ボンターデ」
Comeとはおあがりなさい、と言う事である。それはよく解ったが、後に続いた言葉の意味は何のことだか解らなかった。しかしこの時に言ったアントニオの言葉は後になる迄私の耳に残って消えなかった。「食う」と言うことは人間にとってそれ程重要なものであることは親のすねに噛り付いて労苦を知らなかった私にとって痛切な新しい体験であった。
五
朝飯後の仕事は木のロードをお臍の辺りに当てて、テレーロに散布された珈琲の上を押して歩くのであった。よそ目にはのんき千万な遊び事の様に見えるが、ジリジリと照りつける日光と、煉瓦の温もりとは焼きつけるように暑かった。
一区画の散布された珈琲の上に各一人ずつの労働者が、黙々とロードを押している姿が見えて広大なテレーロは暫く何の音響もない沈黙の世界と化してしまう。ただ時として旋風がくるくると大空にものを巻き上げて行ったり、ぎらぎらと陽炎が立ったりして、この果てしもない様な寂しいモノトンを破った。
私は事務所の真下にある比較的小さな一区の珈琲の上を押して歩いた。困ったのは靴を履いてはならないと言うことであった。堅い珈琲の粒が労働に慣れない柔らかな足の底に当たるのが石の様で、やや厚い毛糸の靴足袋も何のたしにもならなかった。
午後四時近くから、この散布している珈琲を搔き集めて長い畦形の山を作ったり、丸い大きな山に積み重ねたりするので、乾燥場は再び活動の世界を現出する。
サン・パウロ州も冬の日は短い。暮れ方は日本の所謂つるべ落としである。太陽の温熱のある間はできる丈これにさらして、日暮れの冷気を可及的防いでしまうと言うのであるから、そのいそがしさは丁度洪水の様に一度にどっと押し寄せて来る。
監督アントニオの鼻が一層赤くなって来て、苦い顔には皺さえたたみ出される。
「トッカ!トッカ!」(やれやれという意味)
こう叫んでは鼠のようにあちこちと出没極まりない。日雇い人達もこの日暮れ方は怠けようとする者がなかった。及び腰になってロードを握っていた手は勢い込んで珈琲を搔き集めて来ると、珈琲の香りを帯びた土煙が立って鼻を打つ。後に散らばり残った珈琲を箒で掻き寄せて来る人が又一しきり埃を舞い上がらせる。
こうした間を干上がった珈琲を小トロッコ車で掛け声勇ましくTulha(コーヒー貯蔵倉)に向かって走らせて行くものもあれば、竹籠や袋に入れたまま肩に載せて運んで行く者もある。
見よ、珈琲貯蔵倉を中心として全テレーロに放射線を引いた活動の世界!それはさながら戦場そのものであった。
夕陽はだんだん紅を兆してくると、忙しさは一層の度を加えて来る、監督の調子が激しくなり声高になって来る。何時しか支配人メネゴニの引き締まった短躯もあらわれて、乾燥場の空気がいやが上に充実して来る。
たそがれと冷気とが盗人でも入って来る様に、こっそりと人知れず広がって来る。
出来上がった珈琲の山にエンセラード(油布)を掛ける人。最後の珈琲を搔き集めにロードを鳴らす人。一しきり日雇い人達の右往左往がはげしくなって来る。
珈琲採集場から小汽車は珈琲を満載して勢いよくテレーロの引込み線に入って来る。
「明日の朝も肩が痛い程あるわい」
こうつぶやいてほの暗い中にぼんやりして立った時、鐘の音がシュンポラヅの盆地の隅々にまでしみ渡る様な音をふり立てた。
「ワー!ワー!」
それは日雇い人達が一日の労苦から解放された勇ましい凱歌の声であった。
× × ×
へとへとにくたびれた身体を着のみ着のままで寝台に投げて今日一日のことを色々に思い浮かべた。
「まあ、まあ、おれの初舞台は無難であった!」
ふと壁を見ると白アリの土線は元のままに修復されていた。あの土線の中を乳白色の虫が昼夜の差別なく営々として住宅と生活との資料を運搬しているであろう。それは何のためであろう。
「皆、生きんが為だ。生きるという内に生物のミステリーな全目的が含まれている。」
こんなことがうつらうつらと頭に浮かんだかと思うと、いつの間にか深い眠りに落ちて行った。
六
最初の間は出来るだけ自ら進んで難儀な仕事を選んで働いたが、それは到底体力の許すところでなかった。私の疲労は一日、一日と度を増して行った。こんなにして一か月もたったらミイラになってしまう様な気がした。
実際困った。困っても遣り遂げなければならないのだ。労働が終わって自分の部屋に引き上げて寝台の上に腰を下ろすと、何時も泣きたい様な気分に襲われた。私は英雄でも何でもない。極めて尋常な平凡人である。決して自己の立場を小説的に装飾しようとは思わない。訴えるべき知人もなく、読むべき一枚の新聞もない。勿論言葉は少々の単語を知っているに過ぎない。こう言う孤独なやる瀬ない立場にあってもなお大言壮語する…勇気というよりは…寧ろ稚気を持っていなかった。
監督のアントニオは私に就いて何ら特別の命令を受けてなかったと見えて少しの手心も用いなかった。雨の日などは監督の口一つでテレーロに残って雨水で流された珈琲を掃き集めたりする様な遊び半分の仕事はいくらもあったが、私は何時も大勢と一緒になって、軽鉄の沿線や珈琲園などの除草にやられた。リーマ(鑢)もかけていないエンシャーダ(鍬)は徒に力ばかり入って割合に成績が上がらなかった。力そのものの様なバイヤ生まれの黒奴などは乱暴に勢い込んで鍬を引きながら
「オー・ジャポン、オージャポン」
などと呼んで、遅れがちな私を顧みては、その真っ赤な唇を開けて笑った。
「糞!クロンボなどに負けておるもんか」
私は日本語で、こんな事を言ってあせったが、どうしても彼等を抜くことが出来なかった。温かい汗が額をだらだらと流れて目に入った。それを土まみれの手で拭きながら、
「忌々しいなあ」
エンシャーダを杖に棒立ちになって頑健な彼等の勇ましい姿勢を眺めた。
しかし『慣れる』と言うことは恐ろしいものだ。私は段々境遇に適応していくことをさとって来た。いたずらに困難な労働に猪の如く突進するばかりが能ではない。怠けないで絶えず努力する事がプリンシプル(主要)でなければならないのだ。乾燥場の労働も一様ではない。さほど力を用いない注意と根気とを必要とする仕事も少なくない。仕事の成績も重大には相違ないが、私の全能力…つまりベストを尽くすと言うことは、もっと必要なことである。体質により、境遇に従って人は各々異なった天分を持っていることは否めない。
「力で負けたら根気で勝て」
負け惜しみであったかも知れないが、私はこう言う考えから何時も人目に付きやすい場所を選んで働いた。『俺は怠けてはおらんぞ』と言うことを何人にもすぐ認めることが出来る様にしたかったからである。多数の日雇い人の内には随分ずるい怠け者があった。縄煙草を小刀で削り取って唐黍の皮で巻いていたかと思うと『この男はいつも下痢しているのではあるまいか』と思う程大小便に姿をかくした。
支配人メネゴニは一日に一度はきっと私の傍に来て
「コモ・ワイ・エスター・ボン?」(どうです、大丈夫ですか?)
簡単なこう言う断片的な会話には、もう私も慣れてきた。
「エストウ・ベン・ムイト・オブリガード」(ありがとう、大元気です)
出来るだけ感謝の意を示すために、彼等から見て不思議な東洋人の顔に微笑みをたたえて挨拶した。
ともすると、支配人の見えない時もあったが、それは私にとって何とも言えない物寂しい日となった。
七
労働上よりも一層重大な苦難が私を待ち受けていた。それは空腹と戦わなければならないと言うことであった。
乳飲み子の時代と病気との場合を除く二十七年の母国生活に於いて一日に三度の食事を欠かさなかった幸福を今更に感謝する。
サン・パウロ州の珈琲園地方の食事は、早朝カフェー、午前九時朝食、正午カフェー、午後三時夕食、労働終了後カフェーと言う様な習慣になっている。家族を持っているものは珈琲の時パンを取るから差し支えないが、日雇い生活者は二度の食事以外にはカフェーと言っても、小さな珈琲茶碗か、ブリキ製のカネカで一杯飲むだけである。私は朝と夜の珈琲は飲みに行かなかった。十二時のカフェーの時間には監督のお上さんが茶瓶(ブーレ)に入れて夫のアントニオに持って来るので、私もそれを飲んだ。
かって体験のない労働をして、一日に二度の食事、午後三時に食べてから翌朝の九時まで十八時間何物も口に入れられないと言うことは実に容易ならざることであった。私の食欲は異常な率をもって亢進して行った。私は食事の場合に余り食うので羞恥を感ぜずにいられなかった。アントニオはよく
「コメ・マイス」(もっとおあがり)
などと言ってくれたが、お上さんは時々妙な目付きをした。それで私はお上さんが台所に立った折りを見て大皿からご飯を分け取る様な悪知恵を出す様なことをした。或いは私の邪推であったかも
知れないが、イタリア名物マカロナーダを料理した時である。お上さんはナポリ生まれであったから特にマカロン料理が上手であった。私は自分でも驚くほど食った…実際私はいくら食べても腹が一杯になった様な気がしなかった。流石のお上さんも大皿のお代わりを取りに台所に立ちかけて一寸アントニオをふり返ったが、何かイタリア語でしゃべった。人間には確かに六感がある。この時にお上さんが言ったのは、
「この男は何と言う大食であろう」
呆れているよりも寧ろ少々の賄い代を貰ったのでは間に合わんと言う様な、小さな女心から出る気分らしかった。アントニオはそれを叱るような鋭い声を出した。私は耳の根元まで顔を真っ赤にしてしまった。
こんな風で、食事は私にとってこの上のない楽しみでもあったが、一種の嫌な時間となって行った。
何とかして空腹を満たさねばならない。月夜の晩など仕事がすんでからよく四キロメートルスの距離にあるクラビンニヨスと言う町へバナナを買いに行った。
或る時、日雇い仲間の黒人は町に行く私を見て、
「オッセ・ノンテン・メード?」(お前は恐ろしくないか?)
恐ろしいと言うよりも私の空腹が一層私を強迫して止まなかった。バナナは一ダース三百レースに過ぎなかったが、大枚五ミルレースの持ち金は見る見る減じて心細さは日に日に加わって行った。
「バナナが食えなくなったら、どうなるだろう?」
これは嘘のような真実であった。
八
ドクトル・ベント・ブエノ氏は珈琲収穫期間だけ、自ら農場を監視するため、家族を連れてやって来たのは間もないことであった。
丈の高いベント氏は長い顔に鼻と口との間の短いのが目立った。いつも丁寧なやさしい声でゆっくりと物を言う人で、支配人メネゴニの喧嘩する様な荒々しい応対ぶりと比べて、誰の心にも好感を与えた。
或る日ベント氏は乾燥場にロードを押している私を呼んで、珈琲精選場(ベニヒツシオ・デ・カソヘイ)につれて行った。二人のイタリア人が働いていたが、私にこれからここで働くように命じた。
乾燥された珈琲の粒が、その貯蔵庫から巻き上げられて精選せられ、形の大小に応じて別々の管で排出せられて来る。それを六十キロずつの重量にして袋の口を縫う。縫った袋を一方の壁に添って積み重ねる。この二つが珈琲精選場の仕事であった。袋の口を縫うことは女子供にも出来る容易なことであったが、六十キロの袋を二人でその一端を握って重ねて行くことは私にも六、七袋まで位は、さほど困難でなかったが、しかし七袋目となり九袋目となり、堆積が段々と高くなって来るに従って困難の度が増して来た。力よりも二人の調子がうまく揃って、ふっと上に振り上げる一寸した拍子を会得すればよいのであるが、それがどうしても出来なかった。
頑丈な二人のイタリア人は、私のこの如何にも力無げな様子を面白がって、袋を縫うことは自分達でやって堆積する場合のみ必ず
「オ・ジャポン、オ・ジャポン」
と叫んで私を手招いた。私も何とかして笑われたくないと言う意地から、すぐ立ち上がって袋を握った。慣れては行ったが時として袋が中途迄しか上がらないと
「オリャ、アキイ、ジャポン」(これごらん、日本)
と二人のイタリア人は珈琲の袋を軽々と積み重ねて笑った。
「糞!これ位なことはおれにだって出来んと言うことがあるか」
魂限り戦った。疲労の度は乾燥場の比ではなかった。絶え間ないごとごとと言う機械の音響、珈琲の香りをただよわす土埃の飛散、こうしたうす暗い工場の空気は私を半ばヒステリックにし、気管を傷めて、とうとう病臥するに至った。
|
|


