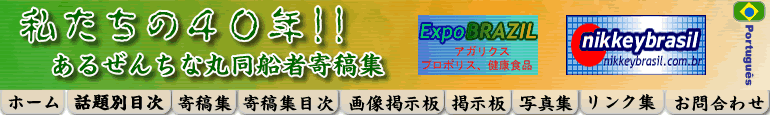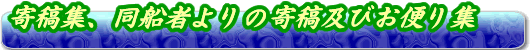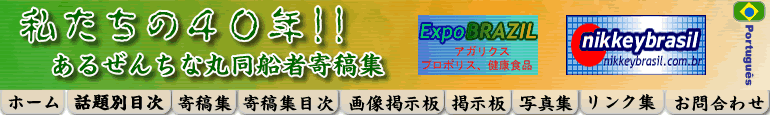|
ブラジル在住のサッカージャーナリスト沢田啓明さんのコラム(2)
|
 |
ブラジル在住のサッカージャーナリスト沢田啓明さん(1955年山口県防府市生まれ。上智大学外国語学部フランス語学科卒業。1986年来伯、サンパウロ在住)は、報知新聞のスポーツ報知に毎週ブラジルのサッカー情報を【カーニバルの熱狂】との題でコラムを掲載しておられますが、1寄稿欄に字数制限があることから3月24日掲載分からその(2)に移して掲載することにしました。寄稿集の125番目に「情熱のブラジルサッカー 華麗・独創・興奮」また211番目に「ジーコ 新たなる挑戦」の著書2冊を紹介させて頂いております。ご参考下さい。写真は、3月にサンパウロの炉辺ごんべいでブラジル国産の東麒麟に焼き鳥でサッカー論議を楽しんだ際に撮らせて頂いたものです。有難う御座います。 |
|
3月24日のスポーツ報知に掲載分。
<楽しみであり恐ろしくもある11年後のW杯>
2014年のW杯がブラジルで開催されることがほぼ確実になった。国際サッカー連盟(FIFA)が2014年W杯を南米で開催することを決定し、これを受けて南米サッカー連盟が「ブラジルを2014年W杯の唯一の開催候補国とする」と発浮オたからである。南米でW杯が行われるのは1978年アルゼンチン大会以来、5回目。ブラジルは1950年に開催している。
南米は、どの国も経済状況が良くない。以前のように世界の各地域の国が立候補し、その中で最良の条件を備えた国が選ばれるという方式ではW杯を開催するチャンスはほとんどなかった。それが、開催地が各大陸の持ち回りとなったことで、再び南米にW杯を開催する機会が訪れた。
本来ならブラジルと並んでアルゼンチンが開催国に名乗りを上げてもおかしくない。しかし、ブラジル以上に経済状況が悪くてW杯どころではない。また、ペルーを中心とするアンデス諸国が共同開催を検討していたが、FIFAが受け入れそうにないことから、消去法でブラジルが残った。
ブラジルにはスタジアムの改修、インフラの整備、治安の改善など問題が山積している。しかし、ブラジル人はサッカーのためであれば何でもやる。国を挙げて準備をするだろうから、何とかなるだろう(と思いたい)。
50年のW杯で、ブラジルは最終戦でウルグアイにまさかの逆転負けを喫して初優勝を逃し、国中が悲嘆に暮れた。いわゆる「マラカナンの悲劇」である。前回果たせなかった地元優勝が実現すればよいが、もしまた負けて「マラカナンの悲劇」の再現となったら、どんなことが起きるのか。
楽しみであると同時に、少し恐ろしくもある。
3月31日のスポーツ報知に掲載分
<サッカー外交国ブラジルの反戦姿勢>
イラク戦争が始まる前日、ラジオのスポーツ番組を聞いていたら、超ベテランのサッカーコーチであるエバリスト・デ・マセードがインタビューに答えていた。
マセードはMFとしてフラメンゴ、バルセロナなどで活躍し、引退後はフラメンゴ、グレミオなどの監督を務めた。また、イラク代浮フ監督として1986年ワールドカップのアジア卵Iを突破し、イラク史上初(そして現在まで唯一)のワールドカップ出場を果たした経歴の持ち主である。
イラク代浮フ監督時代のサダム・フセインとのかかわりについて聞かれたマセードは「大多数のイラク人と同様、彼は大変なサッカー好きだった。流ちょうなスペイン語を話し、通訳抜きでサッカー談議をしたものだ。独裁者かもしれないが、私の仕事に干渉することはなかった」と話した。
そして「もし戦争が始まったら、フセインはどうなると思うか」という質問には「戦争が起こらないことを祈るが、仮に戦争が始まったらフセインは生きてはいられないだろう」と答えていた。
現在、ブラジルは世界の70以上の国にサッカーの選手とコーチを送り出しており、アラブ諸国とは特にコーチの派遣を通じて長い交流がある(例えば、ブラジル代浮フパレイラ監督はクウェートとアラブ首長国連邦の代賦ト督を長く務めた)。また、ブラジルには
アラブ系の移住者がかなりおり、有力クラブの役員にはアラブ系が少なくない。
今回の戦争に対して、ブラジルは政府も国民も一貫して反対している。ブラジルのように世界中から移住者を受け入れ、またサッカーを通じて世界各国と交流していると、どこの国とも敵対する気にならないだろう。同時に、他の国から敵意を持たれる可柏ォも少ない。
世界中から移住者を受け入れていること、そしてサッカーを通じて世界各国と友好を深めていることが、ブラジルにとっては一種の「防衛手段」、あるいは「戦争抑止力」として働いているように思える。
4月7日<美人審判の登場にファンも興奮>
最近、ブラジルのサッカー界で注目を集めている若い女性がいる。アナ・パウラ・
オリベイラ、24歳。サンパウロ州選手権の試合で副審を務め、オフサイドかどうかと
いう際どいプレーをことごとく的確に判定して賞賛された。おまけにスタイル抜群の
美人とあって、ファンが急増している。
ブラジルでは、審判は実に損な役回りを負わされている。間違った判定をしようも
のなら監督、選手から執拗な抗議を受け、ファンからは「泥棒」呼ばわりされ、メ
ディアからも手厳しく批判される。おまけに、正しい判定をしたときでさえ理不尽な
抗議を受けることが珍しくない。しかも、サッカー界は徹底した男性社会で、女性の
審判となると選手もファンもハナから信用していない。女子の試合であればまだし
も、男の、それもプロのトップレベルの試合で女性が審判を務め、そして評価を勝ち
得るというのは大変なことだ。
アナ・パウラは、かつてアマチュアの試合の審判をしていた父親の影響で審判を目
指すようになったという。二年前からプロの試合の副審を務めているが、当初は周囲
の偏見との戦いが続いた。しかし、守備の最終ラインに合わせてポジションを取ると
いう基本を忠実に守り、集中力を絶やさず、微妙なプレーでも冷静に見極めて的確な
判定を下すことで監督、選手、ファン、メディアの信頼と評価を勝ち得てきた。
「試合中に選手からナンパされそうになったことはないか」という不躾な質問に
は、「プロの試合ではめったにないけれど、ユースの試合ではよくあったわ。私に抗
議しているふりをして、話しかけてくるの」と笑って答える。今後の目標について
は、「まず、今年のブラジル全国選手権の試合で高い評価を得たい。そして国際審判
になって、いずれはワールドカップに出場したい」と語る。
すっかり人気者になったとはいえ、ひとたび誤審をすれば容赦のない批判が待ち受
けている。アナ・パウラの挑戦が続く。
4月14日<問題児の扱い方は王国ブラジルに学べ>
エジムンドとエジウャ唐ェ、Jのクラブから離脱した。2人ともチームの主軸とし
て期待されていただけに、クラブ関係者は苦り切っていることだろう。怒っている
ファンも多いに違いない。
ブラジルのサッカー選手の大半は、貧困家庭の出身。きちんとした教育を受けてい
ない者が多く、契約の観念に乏しい。だからこそ、クラブが選手をきちんと管理し、
それと同時に本人のみならず家族を含めた生活面のケアをしてやることが必要とな
る。
ブラジル国内でも、同様のトラブルが起きる。この場合、クラブは選手のワガママ
をそっくり認めたりはしない。裁判に訴えてでも違約金を取ろうとするし、違約金を
払わない場合は他のクラブでプレーできないような法的措置を取る。
エジムンドは、リオとサンパウロの名門5クラブの争奪戦の末、古巣バスコ・ダ・
ガマへの復帰が決まった。一方、エジウャ唐ヘまだ所属クラブが決まっていない。所
有権はフラメンゴにあり、クルゼイロにレンタルされてから柏レイャ汲ノ再レンタル
された。だから、本来であればクルゼイロに戻るべきところなのだが、「クルゼイロ
でプレーするのはイヤ」と言って駄々をこねている。かつて在籍したコリンチャンス
に復帰したいらしいが、コリンチャンスは若手FWが好調なのでエジウャ唐ノ興味を
示していない。
サッカー王国ブラジルは、問題児の宝庫でもある。だから、問題児をどう扱うかに
ついてはそれなりの伝統があり、こういった選手をどう起用するべきかについてもコ
ンセンサスができている。問題児をうまく使いこなせるかどうかが、クラブと監督の
腕の見せ所なのである。
4月21日 <醍醐味詰まったリベルタドーレス杯>
南米クラブ一を争うリベルタドーレス杯のベスト16が決まった。計32チームが4チームずつ8グループに分かれてホームアンドアウエーの総当たりで対戦してきたが、ブラジル勢は出場した4チームがいずれも首位でグループリーグを突破した。
リベルタドーレス杯というのは、なかなか大変な大会である。参加チームが各国を代表する強豪であるのは当然のことながら、アウエーでのプレッシャーが常軌を逸しているし、ボリビア、コロンビア、エクアドル、メキシコといった国で試合をする場合には高度との戦いがある。ボリビアのラパスに至っては3600メートルの高地にあるから、富士山の山頂とさして変わらない高さ。外国のチームは、ロッカールームに酸素ボンベを持ち込んで戦う。
とはいえ、ブラジルのチームが最も警戒するのは、やはりアルゼンチンのチームだ。長年の対戦からブラジル選手の長所と短所を熟知しており、ラフプレーやファウルを交えてブラジル選手のテクニックを封じようとする。そして、いったんリードしたら露骨な時間稼ぎ。これにイライラすると、逆に相手の思うツボとなる。
決勝トーナメント1回戦では、コリンチャンスとリバープレートが激突する。ブラジルとアルゼンチンを代表する名門中の名門だけに、すさまじい戦いとなるだろう。コリンチャンスの入ったブロックには、リバープレートのほかにもボカ・ジュニアーズ、ラシンのアルゼンチン勢が集結した。
一方、サントスのブロックにはコロンビア勢がいる。こちらは相手もさることながら、コロンビアの麻薬カルテルが賭けに加わっていることによる不気味さがある。欧州チャンピオンズ・リーグのような華やかさにこそ欠けるものの、ここにもサッカーのだいご味がある。
4月28日 <凋落パルメイラスに“お葬式”の抗議>
「おまえらみんな、バグダッドに行って死んでこい!」
失点を重ねて肩を落としているパルメイラスの選手たちに向かって、スタンドから痛烈なヤジが飛んだ。サポーターたちは、仲間の一人をクラブの旗でくるみ、横倒しにした体を頭上に持ち上げてスタンドで行進を始めた。お葬式。「栄光のパルメイラスは死んだ」というわけである。そのかたわらで、涙を流しているファンも大勢いる。
ファンが怒り、嘆き悲しむのも無理はない。23日にホームスタジアムで行われたブラジル杯の試合で、名門パルメイラスが格下のヴィトリアに2―7で大敗したのである。
パルメイラスは、1914年にイタリア移民によって設立された総合スポーツクラブ。サンパウロではコリンチャンスに次ぐ人気があり、過去、ブラジル全国選手権で4回優勝している名門中の名門だ。しかし、昨年のブラジル全国選手権で26チーム中24位に終わり、2部に陥落してしまった。このため、監督を更迭し、選手も大きく入れ替えて今シーズンに臨んでいた。
ライバルのコリンチャンスとサントスが南米一を目指してリベルタドーレス杯で快進撃を続けているというのに、パルメイラスは全国選手権の2部で戦わなくてはいけない。それだけで十分に屈辱的なのに、ブラジル杯でも敗退が決定的となってしまった。それでファンの怒りが爆発して、冒頭のような光景になったというわけである。
ブラジルのサッカーファンのひいきチームに対する思い入れは、すさまじい。しかし、単に罵詈雑言(ばりぞうごん)を浴びせるだけではなくて、なかなかユニークな抗議を行うことがある。こういったところも、ブラジルサッカーの面白さの重要な一部分と言ってよいだろう。
5月5日 <ダレッサンドロの挑発にやられたコリンチャンス>
1日に行われたリベルタドーレス杯の決勝トーナメントの試合(アウエー戦)でコリンチャンスが勝てたはずの試合を落とした。アルゼンチンの名門リバープレートと対戦して後半途中まで1点をリード。しかも、相手選手が退場させられたため1人選手が多いという有利な状況にあった。ところが、相手の挑発に乗せられて退場者を出し、これが原因となって逆転負けを喫したのである。
挑発を受けた状況は至って平凡だった。ボールがタッチラインを割ってコリンチャンスのボールとなったのだが、スローインをするはずの左サイドバックのクレベールが体の横にボールを置いたままピッチに座り込んでスパイクのひもを結び直し始めた。これを時間稼ぎと受け取ったリバープレートのMFダレッサンドロが猛然と駆け寄り、クレベールの体の上にのしかかってすさまじい形相でどなりつけると、「早くスローインをしろ」と言わんばかりにボールを押し付けたのである。
ブラジルでは、こんなことをする選手はいない。頭に血が上ったクレベールは、その数分後にダレッサンドロを倒して退場処分を受ける。コリンチャンスはこれで守備のバランスが崩れてミスが続出し、試合の終盤に連続失点を喫して敗れた。
ダレッサンドロは左足の裏側を使ってボールを動かしながら急に方向を変えて相手を抜き去るという独特のドリブルを持つテクニシャン。クレベールに対する行為は計算ずくだっただろう。まだ22歳だが、技術、ずる賢さの両面ですでに超一流の域にある。
アルゼンチンの選手は、うまくて強くてずるい。ブラジルの選手も決してナイーブではないが、アルゼンチンの選手ほどのずるさはない。これが、ブラジルのチームが伝統的にアルゼンチンのチームを苦手にしてきた理由の一つだろう。
コリンチャンスは、14日にホームでリバープレートを迎え撃つ。南米サッカーのエッセンスが詰まったようなすごい試合になりそうだ。
5月12日 <ファンの力で勝ったPK戦>
サッカーでは、ファンのことを「12人目の選手」と呼ぶ。ファンの熱烈な応援が選手を勇気づけ、チームを勝利に導くことが少なくないからである。
このファンの応援が選手1人分どころか2人分にも3人分にも感じられた試合があった。7日に行われたリベルタドーレス杯決勝トーナメントのサントス対ナシオナル(ウルグアイ)戦である。
モンテビデオで行われた第1戦が4―4の引き分けに終わった後の第2戦。サントスの本拠地は超満員となったが、この日のサントスは不運な失点もあって勝ち切れず、2―2の引き分け。勝負はPK戦に持ち越された。
サントスのGKファビオ・コスタがPK戦の行われる側のゴールに向かって歩き始めると、満員の観衆が一斉に彼の名前を叫び始めた。
実は、この日の試合でファビオ・コスタは重大なミスを犯していた。右のタッチライン近くでナシオナルにFKが与えられ、ナシオナルの選手は直接ゴールを狙った。
ところが、クロスが来るものと思い込んでいたこの若いGKがシュートを取り損ねてしまう。仮にこの失点がなければ、サントスが勝っていた試合だった。
それでも、サントス・ファンはファビオ・コスタを責めることなく、声の限りに励ました。そして、奮い立ったファビオ・コスタがこの声援に応える。相手が蹴った4本のPKのうち3本を止めたのである。一方、サントスの選手は全員が成功して、サントスのベスト8進出が決まった。
試合後、ファビオ・コスタは「ファンの後押しのおかげで体が動いてセーブできたんだ。このことは一生忘れない」と言って目を潤ませていた。
サッカーでは、ファンの力で勝つことが間違いなくある。だから、ブラジルのファンは「オレの愛するチームをオレの力で勝たせてやるんだ」と意気込んでスタジアムに向かうのである。
5月19日 <ひいきチームとともに生きるブラジル人>
コリンチャンスはサンパウロ最大の人気クラブで、熱狂的なファンが多いことで知られている。
サンパウロ州選手権で最多優勝回数を誇る強豪だが、南米クラブ王者を争うリベルタドーレス杯ではまだ優勝したことがない。このため、ライバルチームのファンからは「永遠のローカルチーム」と揶揄(やゆ)され、コリンチアーノ(コリンチャンス・ファン)たちは悔しい思いをしてきた。
今年のリベルタドーレス杯でも、決勝トーナメント1回戦でリバープレート(アルゼンチン)に敗れ、姿を消した。アウエーゲームで後半途中まで勝っていたのに、試合終了間際に2点を連取され逆転負け。14日に行われたホームゲームでも先制点を挙げたが、退場者を出して守備のバランスが崩れ、またしても逆転負けを喫してしまった。
試合後、スタンドではいすに座り込み、涙を浮かべてぼう然としているコリンチアーノの姿がそこかしこに見られた。
その翌日、街で友人のコリンチアーノに会ったところ、「昨晩は悔しくてほとんど眠れなかった。おまけに、会社ではパルメイラスやサンパウロFCのファンのやつらから散々にからかわれて頭にきた」と言って憤然としていた。また、私の娘が通う中学校では一人の男の子が欠席し、その母親が「コリンチャンスが負けたせいで、夫と息子がそろって寝込んでいます」と学校に連絡してきたそうだ。
大事な試合に負けたときは誰でもショックを受けるが、じっと耐え忍ぶしかない。ところが、ファンどうしのライバル意識が強いブラジルでは、別のチームのファンからの嘲(ちょう)笑がこれに追い打ちをかける。ブラジルのファンを見ていると、彼らが自分のひいきチームと苦楽をともにして生きていることがよくわかる。
5月26日 <混乱こそブラジルサッカーの醍醐味!?>
先週、ブラジルで「サッカーがなくなるかもしれない緊急事態」が発生した。スタジアムでファンに安全で快適な環境を提供することを義務付けた法律が批准されたところ、ブラジルサッカー協会(CBF)と一部のクラブが「この法律は厳しすぎて順守不可能なので、全国選手権を一時中断する」と発表したのである。
ところが、メディアとファンが猛烈に反発し、CBFと一部クラブを強く批判した。そこで有力クラブの代表者が政府と話し合ったのだが、政府が断固として同法の施行を主張したことから最終的にクラブ側が折れ、全国選手権中断の決定を撤回した。
近年、ブラジルではファンがけんかや事故によって負傷する事件が頻発しており、スタジアムのメンテナンスが悪いこともあって観客数が減少している。ファンを擁護し、クラブ経営の近代化を促す同法が施行されることは、ブラジルサッカーがより健全に運営される端緒となりそうだ。
とはいえ、長年ブラジルサッカーを見ていていまだに不思議なのは、これだけ協会もクラブもいいかげんなのに、どうして相変わらず強いのか、という点である。ブラジルの関係者にこれらの疑問をぶつけると「ブラジルが強いのは選手の質が高いから」で「選手の質が高いのは、いろいろな人種の長所を備えた混血の選手たちが自由な発想でプレーするから」という答えが返ってくる。そして「もしブラジルサッカーがまともに運営されるようになったら、もっともっと強くなる」と口をそろえる。
そうかもしれない。ただ、ブラジルそのものが混乱に満ちた国であり、ブラジル人は混乱の中で問題を解決するのが天才的にうまい。だから、仮にブラジルサッカーがきちんと運営されるようになっても、それがチーム強化や選手育成につながるかどうかはわからないとも思うのだが…。
|
|