|
『回り道をした男たち』三重大学農学部南米三翠同窓会史 徳力啓三さん寄贈
|
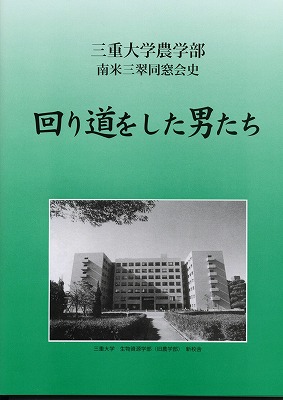 |
日本学生海外移住連盟のメンバー校の一つ三重大学出身者で形成する三翠会の同窓会史が発行された。『回り道をした男たち』の一人徳力啓三さんより貴重な同窓史を送って頂き早速ページを繰っておりますが、徳力さんにお願いして彼の書いた【ブラジルに描く夢】だけでも全文ご紹介したく思います。徳力さんは、1941年に三重県は、松坂城下の商家の次男坊として生れ小学校3年生の頃からブラジル行きを発言していたとの事で長じて松坂工業高校の機械科から三重大学農学部に現役で入学、1964年に学移連の派遣団第5回生として仲間11人と1年間研修、1995年10月三重大卒業、1996年4月にブラジルに移住。その後のブラジルでの生活、定着の過程、現在と未来への展望を自分史として克明に語る。是非皆さんにも読んで頂きたいと思います。
写真は、同窓会史の表紙をお借りしました。尚、ニッケイ新聞の6月12日(土)版にも記事として掲載されていましたのでお借りしました。
|
|
■『回り道をした男たち』三重大学の同窓生ら書く-----------------6月12日(土)
三重大学南米三翠会同窓会は『回り道をした男たち―三重大学農学部南米三翠同窓会史―』を発行した。移住者や派遣者としてブラジル、アルゼンチン、パラグアイに渡った三十人の自分史が収められている。横地実さんは「ブラジルの苦労話が書かれています。あんまり書きたくないことも虚心坦懐、自分の反省も入れつつ書きました」と話し、浅海護也さんは「満蒙開拓の資料はあっても、南米移住者の自分史はあまりない。ある意味で貴重な資料になるのでは」と話した。完成した同書は文協などにはすでに寄贈され、残りは高野書店(コンセリェイロ・フルタード街759番地)に委託されている。
ブラジルに描く夢
総合農科 12回生 徳力啓三
1−序
2−幼少の思い出(1951〜1959)
3−三重大学時代 (1960〜1965)
4−学生海外移住連盟派遣のブラジル研修(1964〜1965)
5−仕事と家庭。ヤンマー社での9年(1967〜1975)
6−ピラガスー農牧時代(1976〜1980)
7−雌伏の時代。再びヤンマー社で。(1981〜1989)
8−マルグザ時代(1990〜1992)
9−独立。ラ・カンターレ社設立。(1993〜今日まで)
10−終わりに
1−序
一昨日、めがねを新調した。普通の老眼鏡とコンピューター専用のめがねである。2年前よりコンピューターを使うようになって、急速に老眼が進んでいる。老眼何するものぞと家の近くのめがね屋で何度となくレンズのみ交換していたが、このたびはチョット用心してめがね専門のミタニで誂えた。
まず、読書用の老眼鏡を掛けて見た。相変わらず、60年も見慣れたいつもの自分の顔があった。次に、コンピューター用のめがねを掛けた。途端に不思議なことが起こった。いつも見慣れた自分の顔でないものが鏡に映っている。確かに自分の顔であるべきなのに、どうしても自分の物と認識したくない、それは深いシワに覆われた我が顔であった。このめがねなかりせば、いつまでも自分は若いと思い込み、更なる夢を追い求めている自分と、いや私もよい年になったのだと思う気持ちが交錯して、複雑な気持ちになった。大いなる発見の一日であり、大きなショックの日でもあった。
まだ自分は若いと思い込み、若い者に負けてはおれないと、研鑚の日々を送っているが、自分を見直し、大いなる反省をするためにも、三重大学在学時代以来の道のりを振り返ってみたいと思う強い動機を与えてくれた出来事であった。
2−幼少の思い出(1951〜1959)
私は1941年、松阪城下は本町、とくりき本店という老舗の次男坊として生まれた。長男が跡取りと決められていて、次男の私は早くから自分の道を開拓すべく育てられたように思う。
先年、日本に帰った時、小学校時代の友人が恩師を招いて同窓会を開いてくれた。その折、願証寺の住職をしている尚チャンが「啓ちゃんは3年生くらいの時に僕はブラジルに行くんだと云っていたなー」と言いだすと、恩師村田先生も、[ほんまにそうやったなー]と合づちを打たれた。
なぜそのような幼少の折から、ブラジル移住を考えていたのか自分でもしかと判らない。松阪のような温暖な、住みやすい地に育ちながらアマゾン開拓を夢みたのは、やはり父の物の見方、考え方を継いだのであろう。
中学校を卒業した時には、はっきりとブラジルに行きたいと親父に言ったのを思い出す。いくらなんでも15才、それは余りにも無謀と、父親に叱られ、それならばと手に職のつく松阪工業学校の機械科に入った。
3年生になって、ブラジル移住は農業経験者か大学卒業者でないと駄目とわかり、無謀と知りつつ、実業校から国立大学への入学を強行するべく勉強を始めた。三重大学農学部に入れなければ、自衛隊に入り実学を学んでからブラジルに行くぞと決め、全然勉強したことのない受験科目を参考書たよりに独学していった。ブラジルへの夢が、まさかの入学を可能にしてしまった。松阪高校という受験校から三重大農学部に入学したのは,その年現役ではたった一人だけ、私のように実業校より現役でストレートに入れたのは、やはり神の恵みとしか思えない。
夢見ればそれは必ず実現するとの信念がこの頃から生まれたように思う。
3−三重大学時代
入学したのは農学部総合農学科、1960年4月のことであった。
大学では何を学んだか。三重大学海外移住研究会を創設し、柔道に時間を割いた。3年生の時には日本海外学生連盟の海外研修制度に応募し、ブラジルを1年間自分の眼で確かめた。今思えば果樹教室の藤村先生は移住研究会の顧問でもあり、私のブラジル研修報告記を卒業論文に置き換えてくださったようだった。大学で学んだものは大きく、そしてブラジルへの道を開いてくれた。農業だけでない、もっと大きな広い目を養い得たと思う。
こうして10才くらいの時から言い出したブラジル行きは準備万端整い、父もこれ以上ブラジル行きを反対することもなく、移住することを賛成してくれた。それにしても親、学校出たばかりの子供を心配をし、ブラジルでの働き口を日本で見つけてくた。ブラジルに進出していたヤンマー・ヂーゼルの子会社に、現地に行けば働かせてもらえるように頼み込んでくれた。
大学在学5年と半年、1995年10月、三重大学を卒業。1996年4月よりサンパウロでの仕事に役に立つようにと、ヤンマー学院研修所で6カ月間の研修を受けた。.
船に乗る前に、ブラジル研修期間中、世話になった三重大の大先輩松尾明義氏が帰国されていて、「向こうで嫁さん探すのは大変だから、一緒に行ってくれるような人がいるのだったら、結婚してゆけよ」とアドバイスしてくださった。それを真に受けてそれならばと、知り合いの女の子を先輩に見せにいったら「それで結構」。
千葉県は銚子の彼女の実家に申し込みに行ったら、まったく突然のことで、「猫の子じゃあるまいし、ホイとはあげられぬ」と父親。母親がとりなしてくれて「それじゃ猫の子あげるよ」まで、時間はかからなかった。友達にお金を貸して貰い婚約指輪だけは自分で買い、後は全てなしであったが、
ブラジル壮行の意図を察し、親族だけの結婚式をあげさせてくれた。移住船が神戸港を出る2週間前のことであった。
新婚旅行をかねて、神戸の移住斡旋所に入所するという慌しさであった。
船に乗ったのが、1966年11月。神戸の港には父、母、親戚の方々、友人知人、沢山の方々が見送りに来てくれた。二度と再び日本には戻れないものと覚悟を決めての船出であった。
新妻との別れは横浜、同じ船に乗る手続きをする間がなく、ひとりだけの旅立ちになってしまった。次の船に乗るようにと言い置いての出発であったが、実際には一年後の再会となってしまった。あの時代こんなことが許されたのだから不思議である。
こうしてアマゾンに入ることを間接的にさまたげた親父の意図は、サンパウロで言葉、習慣を覚え、その上でアマゾンへ行きたかったら行けばよろしかろうとの遠大な親心であった。
4−ブラジル研修
日本学生海外移住連盟の海外研修制度が出来たのが1960年、私はその第5回生として1964年4月に横浜港を出発した。その頃の日本は外貨が乏しく、1年間の海外研修に出かけるのに海外持ち出し枠は僅か200ドル。1ドル360円時代でそのころの72000円は当時の初任給の10カ月分に匹敵したのだから相当の大金、学生の身分で持てる額ではなかった。が、200ドルは200ドル、この金で1年にわたる研修期間を過ごさねばならない。超貧乏旅行は覚悟の上であった。
6月にサントスに着いて、仲間11名はそれぞれの目的地に向かった。
私の研修先はアマゾンはトメアス。胡椒の里であった。サンパウロから遥かかなた3100km。今でこそベレンーブラジリア街道があり、トラック野郎は48時間でぶっ飛ばすというが、その当時はブラジリアに首都が移転したばかりで、ベレン−ブラジリア街道の工事が始まったばかり、荷物満載のトラックの助手席で揺られること19日間の旅となった。満天の星を眺めブラジルに来たという感慨と茫漠たる大地の旅に酔いしれていた若き日の自分の姿をありありと思い出す。ホテルとてなく、運転台で寝起きし、鹿狩りした肉を食べながらのサバイバル旅行がこの研修の最初の難関であった。
トメアスでの研修は約5ケ月、ピメンタ・ド・レイノの収穫期に汗を流し、将来必ず自分もここに戻ってアマゾン開拓の一端を担うのだと研修生活にも熱が入った。同世代の日本人が着々と農園を開き、ピメンタを植え、将来に大きな夢を描いているのを見て、自分の将来をダブらせていた。
研修が終わった後、ブラジル各地に出来ていた日系のコロニアを訪ね歩いた。北伯、東北伯、そして南伯、隣国パラグアイの移住地にまでも足を伸ばした。戦後ブラジルへの移民は1952年に再開されており、私が訪ねた頃は古い移住地で10年前後を経過、新しい移住地ではまだ井戸を掘っているような入植間もないところもあった。全部で23の移住地を訪ねた。多くの人と出会い、色々な苦労話を聞かされ、大変な実学となった。大学で勉強することもひとつ、しかし私にとっては青年時代に見た、海外で働く生き生きした移住者の姿は、これぞ日本人の雄飛だと映った。
どこに行っても、日本の学生さんということで歓迎され、行く先々で泊めてもらい、そして餞別まで頂いた。殆ど無銭旅行に等しい貧乏旅行、よくぞ健康も害さず、危難にも遭遇せずに、10カ月間の旅をこなしたものと思う。
移住地めぐりの最後、パラグアイの移住地を回り、アスンシオンの日本大使館に寄った時には持ち金は底をついていた。その当時の大使の名前は失念したが、そこで頂いた餞別は誠に有難かった。パラグアイからブラジルに再入国した際、世界一の超特大の滝があることを聞いた。フォス・ド・イグアスの町から滝まで、大使に頂戴した餞別をはたきタクシーに乗った。あのスケールの大滝をみて、「ここぞ自分の住む国」と決心したことをイグアスーの滝に日本から観光に来た人を案内するたびに、興奮を交えて話す。あの感動は忘れられるものではない。青年時代の感動が今も続くのは,あの轟々たる力強き水音とともにあるからのように思う。
ブラジル滞在10ケ月、行き帰りの船旅をいれると丸一年。実り多き研修を終え、日本に帰った時の印象は、「日本という国はなんと日本人の多いところか」という見渡す限り日本人しかいない日本の姿であった。
5−移住、そして仕事と家庭。ヤンマー社での9年。
親父の配慮でサンパウロでの仕事先は決まっていた。自分で決めたことではあるが、女房も居る。日本では一度も月給を貰ったことがないのに、生活が始まっていた。まったくアマゾンどころではない環境に納まっている自分をサンパウロに見つけることになった。
就職先はブラジル・ヤンマー社、6カ月の研修を受けてきたのにエンジン一つ直せない。言葉は分からない。分からないことだらけ。年をとった人の忠告はやはりよく聞くものだと実感。多感な実力のない若者が夢だけでは何も出来ない。時間を掛けて実力を養うことこそ、アマゾンへの近道と懸命に仕事に打ち込んだ。
一年が経った頃、新妻・洋子をリオ・デ・ジャネイロの港に迎えに行った。この地でこれから苦労を共にする女房の呼び寄せは2カ月後の船と約束しておきながら、初めから齟齬をきたしていた。ヤンマー社の後藤隆社長の「勉強が先、呼び寄せは一年後」の一言で決まっていた。人生甘いものでないことを充分悟らせるお考えであったと思う。
新婚生活はポロン(半地下の部屋)であった。家具は全て中古、新しいのは女房のみ。冷蔵庫にブラジルの珍しい果物を沢山入れ迎え入れたが、それが女房にとってブラジルでの初の思い出らしく子供達によく話してきかせている。
子供は4人欲しいと願っていた。折角ブラジルに来たのだから2人では駄目、親戚もいないこの地に生き抜いていくには最低4人だ。この考え方は三重大の諸先輩にも通じる考え方らしく、5人、6人もの子供をつくられた先輩が4人もいる。子供を4人と設定したことは大いなる誤りであったかと思うこの頃である。
ヤンマー社の仕事は2年間の技術部での機械修理の後、販売部に移り販売店訪問を2年間続けた。ある時、3週間の販売店訪問の出張から帰ったら目の色が黄色くなっていた。移住者がつかむ病気、急性肝炎である。三重大の諸先輩も10余人のうちの数人が同じ病気に掛かったことを記憶しているが、40日の絶対安静の日々は、気ばかりあせる移住初期の誰もが出会う大きな試練であった。
1968年には長男・アントニオ大介、1970年には次男・アルベルト健介が続いて生まれた。次男は生まれてから半年後、右目は弱視で、他方は全然見えないことが分かった。この次男の存在がこれからの自分の人生に大いなる影響を及ぼすことになるのだが、その当時はそれほど深刻には考えていなかった。
移住してから5年がたち、再びアマゾン行きを検討したが、自分の未熟、次男の眼の治療を考えると、踏み切ることは出来なかった。それにもまして、親父の忠告は「子供達をアマゾンの猿にさせぬようによく考えろ」だった。
仕事は販売促進から販売企画部の設立へと動いていった。社内で初めての企画販売の仕事を引き受けるようになり部下も増えていった。相変わらずアマゾンへの夢は衰えず、休みをとっては3000kmのかなたにある「アマゾン」の様子を、休暇を取ってはぶらりと見に行った。
1973年には長女・ジュリアまゆみが誕生した。
その当時、ブラジルは北伯開発を行う企業には税制の恩典を出していた。農機具業界は豊富な農業融資のため好調な販売に支えられ、ヤンマー社もその時代、順調な販売をし、毎年大きな利益をあげていた。税制の恩典を利用し、アマゾンに農牧会社を興すことを考えていた。
6−ピラグァスー農牧時代
1975年年央、ヤンマー社はピラグァスー農牧会社を買収することになった。その決定を報告する間もなく父は10月逝った。その直後話が決まり、年末には私に現地行きの命が下った。父は今度こそ私のアマゾン入りを安心して許してくれたものと感じていた。
サンパウロから空路ブラジリアに飛び、そこからさらに北の方に700km、世界一の陸の島、バナナル島のブラジル・インヂオ・タピラッペ属の部落にある飛行場に降り立った。南緯10度、アマゾンの一角、アラグアイ河の流域である。熱風が私を迎えてくれた。農場はそこから陸のタクシー・テコテコ(軽飛行機)で30分、初めて農場に入った時の感激は今も忘れられない。農場は、幅18km、長さ42km、面積72000ヘクタールの大農場である。本部には数件の家があったが、後はヤシの葉で葺いた牧童の家が10余軒あるのみ。土地のみ広く、牛もその当時は隣りの農場に預かってもらっており、牧場らしき形さえ、ないに等しい茫漠たる姿であった。
しかし、夢は見つづけるものである。
熱帯の文化も何もないところに、ヤンマーの職員は誰も行きたがらなかった。唯一人アマゾン気違いの私がいた。こうして、私のアマゾン入りは、天が幸運を運んでくるが如く、実現したのだった。1975年3月、日本人の職員5人を新規に選び2100kmの悪路を経て、堂々と農場へ入った。迎えたくれたのは30匹余のブラジル・ダチョー−エマの大群だった。自然のそのもののピラグァスー農園は私たちの持ち込んだブルドーザーやトラクターの騒音で動物達はたちまち居なくなり、時たまジャボチ(陸亀)や狐が顔を出すだけになってしまった。あちこちに開けられた道路や牧柵が開発の跡を物語ったていた。隣の農場に預かってもらっていた牛群は4500頭、たちまちにして大牧場主になった私はその時、35才であった。急がば回れの諺とおり、移住したいと言い出してから15年掛かって移住したが、今度はブラジルに着いてから、僅か9年で牧場主となった。
1976年には3男・アンドレ耕介が我が家のメンバーとなり、子供4人が揃った。しかし、乳飲み子を連れて原始林の開拓最前線に入るわけにはいかない。農場本部の諸設備−本部建物から、売店、倉庫、製材所、肉屋、勿論本部職員用のレンガ建ての家屋、牧童用の簡易住居など無数の建物を作り、学校、カッペイラ(小教会)、小動物園まで作り、一応の生活が出来るようになったところで、家族を農場に呼んだ。
1980年年末までの5年間、短い期間であったが、私のアマゾン開拓は熱烈な勢いで続いた。
北米の西部開拓前線さながらの牧場開拓であったが、私が農場長を勤めていた間に7000ヘクタールの牧草化を進め、750kmに及ぶ牧柵をつけた。牛も9000頭にまでなったが、入植当時より問題になっていた先住者問題が、5年も経つのにまだくすぶっていた。農場の大親分の私が正月休みに家族を連れてサンパウロに戻っている留守に事故が起きた。ポッセイロ(先住者)の二世達が農場側の土地監視員を射殺、労働者組合、過激な教会関係者、北マット・グロッソ州の州議員までが飛行機で飛来し、牧場主の非を叫び、民衆をあおった。平和破られ、今にも先住者が農場を襲うような状況にまで発展した。ライフルと拳銃で武装した数人のボデイ・ガードたちに身辺警護をされていては農場内も自由に歩けない、そんな恐ろしい対立の3カ月が過ぎた。私が農場にとどまる限り、農場の運営は不可と判断されたヤンマー社社長の決断で、私はそこから退去せざるをえなかった。平和な仕事が地獄に変わっていた。
私の夢はそこで潰えた。
今考えると、これも親父の配慮かと思う。あのまま農場の中で自分の思いとおり何でも出来る「バカ天狗」になっていたら、子供の教育も出来ず、医者のいないところで家族の一人位の犠牲者が出ていたかもしれない。
家族全員、皆元気でアマゾンの農場暮らしを経験出来たことこそ、私共の幸せとせねばならない。
農場で満天の星を見て、一番末っ子の耕介が「空にワニがいる」と言っテ家に駆け込んできたことがある。農場内の川べりを車で歩いていると、ライトの光を受けたワニの眼が赤く光るのを覚えていて、空を見上げてそのような発想が浮かんだのであろう。
次男健介はトカーノ(大嘴鳥)が家の横に成っていたパパイヤを食べに来ると、猿の如く、急いでパパイヤの木にとびつき、トカーノと競争して、丁度熟しかけた実を採ったものだ。
子供達にはそれぞれに、数限りない農場での経験が思い出として今も生きている。
7−再びヤンマー社へ。雌伏の時代
サンパウロに戻っても、しばらくはピラグァスー農場の運営を遠隔操作していた。夢よもう一度の気持ちがないでもなかったが、平和な開拓を望んでいたわりには、自然を壊し、隣人と摩擦を起こした。確かに一つの町を興した。農場内の一角1500ヘクタールを市街地に譲渡したところが、現在、北マット・グロッソ州の東北に位置するポルト・アレグレ・デ・ノルテというブラジルの地図にも載っている町である。開拓を経験したことにはなったが、私の心には何か満たされないものが残り、なぜこのような間違いが起こったのか、模索していた。
その頃、サンパウロ市北部に住居を構えていたが、イミリン日伯文化協会の会員で隣人の日本人が日本のモラロジー(最高道徳)という教えを学ばないかと誘ってくれた。研鑚を積むにつれ、ピラグァスーでの私の心使いは大いなる間違いを犯していたことに気がついた。「我が、我が」という気持ちが強すぎた。世のため、人のために働く気持ちがなく、唯前に進むのみ、まるで馬車馬であった。周りの人はさぞや迷惑したことであろう。家族のものも不自由をこらえ、私の意のままにさせてくれていた。周りを気使う心くばりが不足していたことに気がついた。
1981年、ヤンマー本社の仕事に再び組み込まれ、販売部、輸出部、社長室と実業をこなしながら、心の勉強も続けていった。
折りしも1980年代の好況に支えられ、ヤンマー社の業績は伸びに伸びた。利益も大きく出、エンジンを作るもとになる鋳物用銑鉄を自社で生産出来ないかと社長室中心に検討が始まった。再度私に出番が巡ってきた。
|
|


