|
杉野忠夫博士の移住監督紀行文 『南米開拓前線を行く』 野口 紘一さんより配信。(2)
|
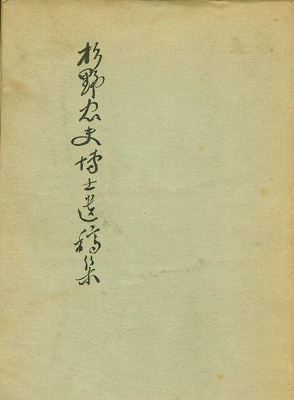 |
杉野先生の残された著作を毎日ご自分で叩きデジタル化を図っておられる野口さんの努力と根気に驚異を覚えますが、野口さんは、『杉野先生が逝去されて40年もたちます、私が歳をとるのはあたり前です。セッセト毎晩、キーボードを叩いていますが週末は遅くまで、真夜中を過ぎるまでイスに座って叩いていますが、何か先生の心がひしひしと感じてくるのには驚きます。』と説明されています。直接お会いする機会がなかった杉野先生ですが、我々移住を目指す学生にはその理想と理論付けをして下さった偉大なる指導者で杉野先生に直接訓育を受けられる農大生を羨ましく思っていた一人です。第2回目の配信をアップして置きます。
写真は、野口さんから送って頂いた杉野先生の著作本の侮˧ナす。
|
|
フラム地区の踏査から得たもの (続き)
パラグワイのような小さな国、そして、人口わずか3万5000千という一地方都市にすぎないエンカルナシオン市の郊外で、トマトやスイカで笑いがとまらないくらい現金がはいる成功者は、10戸や20戸の入植者の時代にはめずらしくもないが、300戸にもふくれあがったら、たちまちトマトの洪水、スイカの洪水である。移住地の調査には、何が出来るかと言う事とともに、何を作れば確実に収入が入るかという経済調査、それも国際経済的視野にたって判断する調査が絶対に必要である。しかしながら、かりにそうした調査がして有ったとしても、開拓によって急激に新しい生産がおこなわれる場合には、市場の混乱がおこり価格の沫獅竅A円滑な商業・金融のルートが同じテンポで開かれず、ズレがィきてくる事は常識として知っておく必要がある。
すべての受け入れ態勢が整って、移住者が生産し出荷さえすれば、計画どおりの現金収入が確保されることは理想であるが、現在の段階では、(将来はそうなる事を希望するが) なかなか困難と考えられる。
それほど受入れ国の準備も、また、送り出す日本側の用意も不充分と思う。
そうすると、結局、こうした場面にあたってたじろがない心がまえ、開拓方式をもって、開拓を進めていくよりほかに方法がない、また、たとえ、そうした用意万端は整ったからと言って、それで開拓が成功するかというと、決してそうではない。パラグワイの例をみても、57年度産の小麦が収穫期に雨が多くて乾燥不助ェとなり、検査に合格しないものが多数出たのが大きな原因であった。
農業が天候に支配される事の大きい産業であるだけに良いこともあるが、泣かなければならない年もある。今日の日本の稲作の様に米価が保障されているために、昔の様に豊作貧乏という事はなくなっても、台風が一度本土に上陸したとなれば、たちまち大風水害となって惨状を呈する。開拓の道に進む者は、こうした困難をものともせずに進む、たくましい精神を持って進まなければならない。
どのような自然の脅威や経済の変動、さらには政治や治安の不安に出会ってもビクともしない心がまえをして行くのが当然と考える。かつての満州への100万戸移住という民族の大行進には、その覚悟が要求されていた。
そして何叙怩ニ言う同胞が、その要求にこたえて奮起した歴史は、まだそう遠い昔のことではない。国や国策機関に陳情するのがむだであるとは言わないが、頼るべきものは自分自身であるということを骨髄に刻みこんでゆかなければ、成功者にはなれないということが開拓者の金科玉条であることを、私はしみじみと味わされたのである。(17)
フラム開拓地の二つの分町計画
さて、地区内を泊まり歩いていて、わたしは大変な有益な研究を沢山する事ができた。それは世間ですでに有名になっている広島沼隈町の分町計画と、高知県大正町の分町計画の比較であるが、両方とも分町計画という点で一致している。そして、入植がだいぶ同じ時期で、昭和32年の7月上句に、隣接する地区に入植したのである。
戸数も私が訪問したとき、だいたい同じくらいで、大正町は70戸、沼隈町は95戸であった。
ところが、それからちょうど7ヶ月たった時に私が訪問したわけであるが、大正町の方は開拓作付け面積が一戸平均9ヘクタール、沼隈町は、4.5ヘクタール、ちょうど沼隈町は大正町の半分にも達していないのである。
そして営農生活の方針を見ると、大正町の方は、入植5ヵ年の現金支出は、塩と石油と石鹸だけで、食料は完全自給を目標とするとのことであった。それで、水稲を一人当り3アールから5アールで、米も食べられる様にして、自給用畑として3ヘクタール、換金作物としてマテ茶、油桐、ナランハ(ミカン)を7ヘクタール。これが生育するまでは(5年間) その間作に小麦2ヘクタール(1回作)、トウモロコシ(2回作) 5ヘクタールを短期の換金作物とし、その他に、一世帯2ヘクタールのアルファルファーの放牧地、間作にマンジョカ(1ヘクタール)以上を作付けし、畜力用の馬のほか、豚、鶏を飼い、ブドウ100本、バナナ50本は自家用という計画をたて、着々とその苗の育成につとめているありさまである。
この大正町には先にブエノスアイレスで聞いたような暗い影は少しもなく、一応10ヘクタールの開拓がすめば、次ぎは雇用移民を呼び寄せようという嵐閧ナ、25ヘクタールの分譲地の半分は自家労力で直営し、半分は雇用農によって歩合耕作をして、それをその人々の自立のための前進基地として利用させるとともに、自家の経済力を培養しようという計画と考えられる。だから、少しぐらいに小麦の滞貨があっても驚かないで落着いているのである。
それにひきかえて、沼隈町の方は、開拓の進度そのものは大正町の半分くらいと言う有り様であり、空気のどことなく悲惨なものがただよっていることを感ぜずにはおれない。この差はどこからきたものか、それが問題である。
先ず第一に、団員の告ャがまったく対照的である。母国の大正町は、高知県の山村であり、人口の増加と生活程度の向上が山林資源の急激な欠乏をきたし、どのような更生策も不可狽ニいう壁にぶち当たった住民の総意を背景としての分町運動であり、団員はたくましい山林の労働に鍛えられた人々で、天を圧するような、うっそうたる原始林を見て『これはしめた!』と喜びを隠しきれなかったという人々である。
それに反して沼隈町は広島県でも有数の港町で、尾道に接する海運業が盛んなところであり、移住者の中心をなすのはその町の人々であり、真の農業経験者は五分の一に過ぎないと奄ウれていたのである。
第二に、大正町では農家に生まれ、小学校卒業以来、役場の給仕を振り出しにたたき上げ、無冠の町長といわれた助役の山脇敏麿氏自身が全団員の信望を一身に集めて、みずから団長として陣頭指揮をしているのに対して、沼隈町は農業の経験のない立命館大学文学部出身の心理学者森太光氏と、沼隈町の前町長神原氏の親戚筋で、尾道の呉服屋の若旦那であったという小林氏が、団長および副団長として赴任してこれらたというのであるから、まったく対照的である。
第三には、大正町では、母国の町と農協が全力をあげて移住者の財産処分を有利におこない、いずれも相当の資金を準備してきているのに対して、沼隈町では、この計画の企画の推進も前町長であり、沼隈町の最大の財閥である神原汽船株式会社社長の神原氏個人が中心で、彼が土地購入費も営農生活資金も全部用意して、移住者は徒手空拳で行って働き、その生産物を組合に出荷すればよいと言うめずらしい方式をとった点である。この方式を神原氏が考えつかれたことは、耕地が乏しく、漁業や造船業や、運送業によって生活している瀬戸内海沿岸の人口過剰の町村の二、三男対策として、またいったん、不況に見まわれた時の対策として、海外に広い土地を用意しようという遠大な理想に立脚したものである。そのために海運や造船で得た利益を投げ出して、沼隈町の人々の永遠の幸福をはかろうとされた事は、現代資本家の模範とすべきである。さらに、私財を投じてこの原始林の中に、設備の完備した病院を寄付し、京都大学の結核研究所の栃木医学博士を院長に赴任させるなど、ちょっと真似のできない仕事をされている。
しかし、その結果はどうかといえば、開拓は進まず、生産はあがらず、販路は狭くて自立の階段は遠く、会社からの救援資金の到着を待つばかりと言うことになったのが、色々なデマの原因となったのである。
私が訪問した時は、ちょうどその絶頂であったように見えた。その後、真相が母県の広島県にも伝わり、県も積極的に救援に乗り出し、またいちばん心配されたトウモロコシも販売されて現金収入も入り再生の道へ進んだと、最近の便りにあったので私も安心した。
この二つの型の分町計画は、今後、こうした計画を進めるうえに非常によい参考になるであろう。そしてまた、色々なデマまで飛んで、関係者を驚かせたことも相当に大きな効果があったのではなかろうか。
それは、あとで日本に帰って聞いたのであるが、日本移住振興会社では、もちろん最初からエンカルナシオンに倉庫を建てたり、トラックを用意したり、必要な場合には収穫物の売却完了の前に内金を立替えして金融の便をはかったり、道路の修理費を補助したり、色々考えて、開拓課長に資金を持たせて出張させていたそうであるが、私が移住地を出発した後、一週間ほどして到着されたそうで、問題の大半が解決した上に、農林省の調査官の中田技官も私のすぐ後からやって来て、トウモロコシの滞貨の山に驚いて農林省に報告された。
そこで農林省はさっそく船をまわして、1,500トンを買いあげたとのことで、その後、フラムからは明るい便りが次々と来るようになった。
この経過から見ても、国策としておこなわれつつある開拓事業は、決して棄民ではない事がよくわかる。しかし、戦争の場合でも、時として弾薬が不足して苦戦におちいったりすることがある。また、正確な情報が遅くなって、一部隊が孤立無援の苦難の場に立つこともあるように、困難はつきものと覚悟しなければならない。
遠い他国の未知の原始林に、明日の理想境を建設するこの聖業にも、創業の難は当然のことと覚悟するべきであろう。この苦難を出来るだけ少なくするように、計画もすべきであるが、いくら装備や計画がよく、名将がいても、戦意と体力の無い兵隊ではどうにもならないであろう。
移住者の量より、質と言うことが、日本の移住者を迎えようという国から強く要望されていることは、あえてその国のためばかりではない。
開拓者その人のためでもあり、また日本の海外移住者全体の信用のためでもあると思うのである。
原始林を克服する戦後の青年たち
南米大陸への上陸第一歩、私達一行を襲った不安の嵐も、現地視察をして家長達の不屈の開拓魂の前にはやがて収まったのである。
その事について、ここにひと言述べたいのは、一行の中に北海道の冷害に痛めつけられて、見切りをつけて移住して来た人々がいたことである。それは、笹尾、高橋、小矢沢という三家族の方であったが、北海道の原生林と取り組み、寒冷な風雪をしのぎ、短い夏には長い北半球の日の下で汗を流し、火山灰や泥炭や湿地と戦ってきたこの一家は、世界無比といわれる肥沃なテーラロシアの厚い地層と、1ヘクタール三本あれば、開拓費をおぎなえると言われる熱帯硬木の生い茂る原生林を見、一戸当り75ヘクタールまでは40万たらずで分譲できるというこの土地を見て、明日からでも天幕を張って山へはいろうと言う張り切りかたであった。これはフラムの話しばかりではない。
私は今度の踏査旅行で至るところに、北海道からきた移住者のたくましい成功の姿を見せつけられてきた。かっての日本のフロンテイーヤは北海道であり、日本人の中で一番強くフロンティーヤ・スピリット(開拓精神)を持っているのは北海道人ではなかろうかと言うことを考えていた私は、至る所にそうした実例を見て、この仮説の正しいことを信ずる事ができた。この事は、今後日本の海外進出の場合によく考える必要のある問題であろう。そして、この人々が推進力となって、一行は関西からきた二家族をエンカルナシオンの町の収容所に残して、私の滞在中に早くも入山してしまったのである。
その一行の中に、年は20歳、農業高校を出たばかりの紅顔の青年がいた。お父さんのお話では、『この子が学校で南米の話しを聞いてきて、どうしても行こうと言うので、とうとう家族全員で来てしまった』と言うことであったが、その若さと健康に恵まれた、はちきれそうな身体に似ぬ、白皙紅唇の美青年で、口数も少なく素人芝居の女形にうってつけのような人柄の、この人のどこに、それだけのファイトが潜んでいるのだろうと思ったのである。
名は順、姓は高橋。上川郡美瑛町出身の青年である。今ごろは、きっと、父母弟妹を助けて原始林の開拓に余念のないことだろう。
こうした若き戦士は北海道の青年ばかりではない。フラムでは私は東京の町の真中から単身飛びこんできて、頑張っているインテリ青年にも会った。私は戦後の都会青年に対する一部の人々の評価が間違っている事を、深くこの人から受けたのである。
ちょうどブラジル丸がロスアンゼルス港を出て、南へ南へとメキシコの沖合いを下っていく頃であった。緯度はそろそろ亜熱帯にはいって船内は蒸し暑くなったので、皆甲板の日陰に涼をとりはじめた頃、静かにひとりで海を眺めている青年に気が付いた。私は何か慰めずにはおれない気持ちになって、その青年に近付いていった。彼は、この三月に東京都立の園芸高校を卒業するはずであったが、学校の特別のはからいで早期に卒業させてもらって12月出航のブラジル丸で、いまパラグワイへ兄さんの応援に行くという片倉君であった。お父さんは、日比谷の三信ビルに事務所をもつ貿易商。
なに不自由なく、坊ちゃん生活をしてきたらしいおっとりした人柄で、無口な青年である。この片倉君を迎えに来た兄さんと、エンカルナシオンの収容所で会ったとき、私はまた驚いた。兄さんという人も、まだ25歳にはなっていないと思われる独身青年である。彼は32年、フラム入植が開始された時、誰かの告ャ家族として法政大学を中退して、独身青年40余人とともに入植した一人であった。彼の話しによると、いっしょに来た若い連中で残っているのは自分だけだと言う事であった。彼は何人かのパラグワイ人と掘立小屋に起居寝食をともにして原始林を開き、弟を呼んだと言うのであった。私はそのたくましい身体と、色々な事業計画を語る希望にあふれた眼差しと、久しぶりに兄弟相擁し得た喜びにみちた若々しい声にすっかり魅せられてしまったのである。
まったく残念なことは、彼の自慢の片倉農場を訪問することが出来なかった事であるがその後、東京へ帰って彼等のご両親にお会いして現地 の模様をお伝えした時の話では、兄弟ふたり力を合わせて着々と農場を完成し、今度はお父さんを呼び寄せて何か事業を営む計画中であるとの便りがあったと伺って、あの兄弟ならやりそうな事だと思ったのである。ここで、片倉青年から聞いた話であるが、「独身青年が逃げたと世間で悪くいうけれども、告ャ家族の一員として残らなかったというだけで、南米から日本へ逃げたものは一人もいない。皆それぞれの理想を追って努力しているので、『今にみろ!』というのが僕達の合言葉です」と教えてくれた。
フラムから逃げだして南米大陸を横断し、アマゾン上流を経てべネズエラに達して、そこでとうとう捕まった三人組の青年も、実は東京都立新宿高校出の20歳を出たばかりの青年達であったそうである。そして、この三人組は旅券も旅費もなく、どこをどうやって行ったか、きっと他日すばらしい冒険旅行記がベストセラーになるかもしれないが、産業経済新聞社の南米踏破隊がベネズエラで会ったとき、ベネズエラ政府はその勇気をたたえ、特別に入国許可をあたえ、政府高官の所有する高原の大農場の管理をさせていたと言うことであった。「今に見ろ!」という不屈の魂がアプレアプレといわれる青年の中に燃えていることを、ここにも見ることができた。
私はアルゼンチンのガルアッぺとボリビアで崇高な理想に燃えて、黙々と開拓の鍬を握っている拓殖大学の若い卒業生に会う事ができた。この両君のことを次ぎに述べることにしよう。
拓殖大学の伝統の火は消えず
戦前、日本の海外発展に多くの人材を送った拓殖大学も、戦後の拓殖教育弾圧の嵐の中で、一時はその名称さえも紅陵大学と変えざるを得なかったことは、もはや昔話で、いまは、伝統ある拓殖大学の名に復し、矢部総長のもとに着々と復興の巨歩を踏み出しつつあるものの、いまだ拓殖学科復活の知らせを聞かないが、さすがに伝統は争われないもので、卒業生は三々五々、南米の新天地に民族の新しい運命を開拓しようと懸命の努力を傾けている尊い姿に接することができたことは、同じ使命感のもとに、青年の養成を目的としてきた私にとっては喜びにたえないところであった。
『農大からも若い諸君を送りますから、よろしくお願い致しますよ。』『承知しました。南米の原生林には学閥はありませんよ。』しかり、学閥くそくらえである。
その一人は、私がエンカルナシオンでの仕事が一段落して、アスンシォンへ出発する直前の寸暇をさいて、対岸アルゼンチン領に渡ってポサダスに一泊し、話しに聞くオベラの紅茶王、帰山農場を訪問したのち、ガルアッぺにある亞拓組合の経営する開拓実習農場で会った場長、藤田京作君である。彼は、福岡県の大地主の長男で、拓殖大学を卒業後、昭和30年にアルゼンチン邦人の結成した亞拓組合の呼び寄せで、単身アルゼンチンに渡り、オベラの帰山農場の実習生として、原始林の開拓からはじめたのである。そしてまもなく夫人を郷里から呼び、人里はなれた原始林に懸命の開拓の斧を振るっていた間に、その真面目な人格と、不屈の精神とが高く評価される日が来たのである。
それはアルゼンチン同胞の大親分、片山良平氏(亞拓組合理事長)が、アルゼンチンの同胞成功者を説き、さらにアルゼンチン政府を動かして、アルゼンチン国内に、日本人の入植許可を得て、その第一着手として、ミッショネス州に土地を求め、80戸の入植者を昭和33年度から入植させるにあたり、その指導のため、ガルアッぺ移住地の中に、開拓実習
農場を設け、その場長として彼を起用したのであった。
この開拓実習農場は、200ヘクタールの原始林である。彼は、ここに昭和30年9月、単身のりこみ、まず、原始林の山焼きからはじめてすでに20ヘクタールを開き、実習生を迎えるべき家を建て、開拓者に供給するマテ茶の苗23万本を仕立て、受け入れの準備をしたのである。
亞拓組合の開拓実習場という国zは、実に面白いしくみで、実習生の宿舎というのがそのまま開拓者の個人住宅のモデルで、木造の頑丈なバンガロー風の洋館なのである。
だから家族ぐるみの実習生も可狽ナ、すでに3家族が入っていた。そして、200ヘクタールの原始林の開拓や育苗園の管理の仕事そのものが実習内容で、それは地方並みの標準賃金が支払われるほかに、一家族当り2ヘクタールくらいの自給農場が、各自の試験農場として貸され、実習期間はだいたい1ヵ年を嵐閧オ、その間に農業をならい、いくらかの資金を作り、それから入植するという方法である。
現地の開拓訓練の方法として、まことに面白いやりかたであるが、藤田君はいわゆる訓練所長型ではなく、親切な隣り組長といったやり方で人々を指導しており、それでいて実習農場は黒字という経営手腕の持ち主で、驚くべき人材である。
のちにブエノスアイレスで片山良平理事長に会ったとき、『あなたは実によい人を持っていますね』といったら、片山さんは『あんなのはめったに居ませんよ』といっておられたが、藤田君のバンガローに3日も居候をした私は、彼からしっかりとしたフロンテイア・スピリットの洗礼を受けたのであった。
次ぎのひとりは、3月30日、ボリビアのサンフアン地区の原生林の中に建設中の移住地で会った鳥崎清冶君である。
このサンフアンと言う所は、ボリビアの東半を占める農業州サンタクルス州(広さは日本とだいたい同じ様であるが、人口はわずか30万、アマゾン河の上流ブラジル台地につながる肥沃で平坦な亜熱帯森林地帯)の首府、人口3万5千のサンタクルスの東北方130キロの地点に有る戦後はじめて、日本とボリビア共和国との間に結ばれた移住協定によって出来た最初の移住地である。ボリビア政府は日本人家族当り、50ヘクタールの原始林を無償でくれて、ここに300家族を入れられる1万5千ヘクタールの移住地が設定され、昭和30年の7月、その第一陣が河を渡って苦労をかさねて入植したという所である。私が訪問した時は、すでに50戸が土地の個人配分を終り、8戸の分家ができ、後続部隊が共同宿舎に何世帯かいて、開拓中と言う段階であった。この分家が鳥崎君である。
彼は誰かの告ャ家族としてきて、分家したのであり、まだ単身のままであるが、いまなお暗い亜熱帯の原始林の中に掘立小屋を建て、黙々として伐木、山焼き、陸稲の播種をおこない、すでに独立して2ヘクタールの陸稲を撒き付けたといっていた。この辺は、とても良く陸稲がとれるうえに、共同で脱穀精米して、サンタクルスへ出荷すれば良い値で売れるので、パラグワイのような問題はみあたらなかった。
彼は50ヘクタールの原始林を開いて、ここを拓大の海外実習地にするのだと張りきっていた。『惰夫をして起こしむ』という文句があるが、まったく彼の奮闘ぶりは開拓地の中で感心しない人はいなかった。
拓殖大学は本当に良い卒業生をもったものだと、その前途を祝福しないではいられない。
こうした先駆者のかかげつつある伝統の火が、ますます燃え上がって行くように、心から祈りながらサンフアンを後にしたのであるが、ボリビア開拓運動がようやく軌道にのった今日、鳥崎君の夢の実現も遠いことではなかろう。
願わくは、拓殖大学の学生諸君が奮起して、彼に続かれんことを。
|
|


