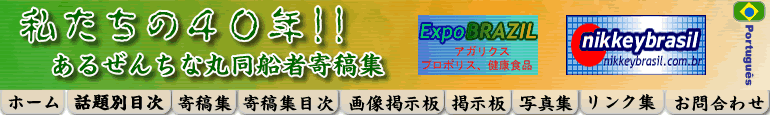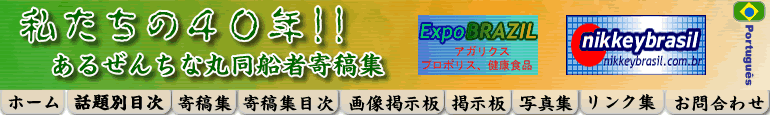|
���҂����w�K�C�W���Q�x�|�Ăђ˖{���q����|�u���W���֘A��ƉƂł�����y�j�b�P�C�V�����]�ځz�R
�˖{���q�����ɂ́u�N���[�x�E�h�E�u���W���v�g�o�ɂ���R��ē���̃��b�Z�[�W��]�ڂ��Ēu���܂��B
GAIJIN 2�`�R��ē���̃��b�Z�[�W
�@���{�Ŗڂ̓�����ɂ����u�o�҂��v�Ƃ������ۂɂ́A�ӂ��̖ʂ�����܂����B�ЂƂ́A���n�u���W���l�����{�ō������邱�Ƃ��ł���Ƃ������ƁB�����ЂƂ́A�ނ玩�g���u���W���l�ł��邱�Ƃ��ĔF���������Ƃł��B�uGAIJIN�`���R�ւ̓��v�ł��A���n�l�̃u���W���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�[�͂ЂƂ̃e�[�}�ł������A���͍Ăт��̃e�[�}�ʼnf��𐧍삷�鎞�����}���Ă���Ǝ������܂����B
�@���łɉߋ��̘b�ł����A�����g�u���W���Ő��܂�AGAIJIN�ƌĂ�Ă��܂����B���ꂪ�����ǂꂾ�����������́A�����ł��͂��肵��܂���B�{���ɁA���낢��ȈӖ��ŏ����܂����B���܂ł����A���̓u���W���Љ�ɂ����ău���W���l�ł���ƔF�߂��Ă��܂����A�������g�ł��悭�����ł��Ȃ��C�����A�܂莩���̐��܂ꂽ����GAIJIN�ƌĂ�Ă��܂��C������\���������ƍl���Ă��܂����B
�@���������u�悭�����ł��Ȃ��C�����v�Ƃ́A���n�l�ɂ����炸�A��葽���̃u���W���l�������Ă�����̂ł��B�u���W���ł́A����قǑ��l�ő��ʂȕ���������������Ă���̂ł��B����Ԃ��A�������������I�ȑ��l�����u���W���l�𖣗͓I�ɂ��Ă���悤�ɂ��v���܂��B
�@�������u���W���l�͂��낢��ȕ������班�����e�����Ă��܂��B���ꂱ���u���W���̕����ł���A�������ɂƂ��č��Y�ł��邱�Ƃ��m�M����ׂ��ł��B���낢��ȕ����������肠�����Ƃɂ���āA�������͋�ʂ��s�\�ȑ��݂Ȃ̂ł���A���ꂪ�������̃I���W�i���e�B�[�Ȃ̂ł��B
|
|
|
 |
�v���o�́y��Ăւ̗��s�z���c�i�q����̂g�o���]��
1935�N���܂�̏��c�i�q����́A�җ�̂��j���ɑ��q����B���瑡��ꂽ�p�\�R�����u�e�F��Ƃ��ė����グ��ꂽ�w��������̕����x(9��1������17210��̃A�N�Z�X���L�^�j�����J���Ă�����B�Ƃ�������w��������40�N!!�xHP�ւ̏������݂�����A��肢���ĂƂ��������HP���̒��ɂ���y��Ă̗��s�z�̏����o���̕�����]�ڂ����Ē������ɂ��܂����B���̑����́Awww.asahi-net.or.jp/~kp7t-syud�ł����������B��R�̎ʐ^�Ƌ��ɐ��m�Ŋy������X�̏Z��ł��鍑���Љ�ĉ������Ă��܂��B����F����ɂ��ǂ�Œ����������s�L�ł��B�C�O�A�X�̑�̓���͈����ł��B�ʐ^��2000�N�ɃA���[���`���̖q��ŎB��ꂽ�n��̎p�Łu���肢�擮���Ē��Ձv�Ƃ��@��������Ă���Ƃ��낾�����ł��B
|
|
|
 |
���{�H�̃t�����e�B�A�@�g�H�̈ږ��j�h�y�j�b�P�C�V���A�ځz���̓]�ځB
�j�b�P�C�V����5��8�����7���Q�����A13��ɓn��A�ڂœ��{�H�̃t�����e�B�A�̑�Ŗʔ��������A�ڂ��f�ڂ���Ă���B����̃S�[���[�A�����A�₫���A�Е�(�Ԕ~)�A�a�َq���{���{�ږ��ɂ��u���W���Ɏ������܂�蒅�������{�H�ɕt���Ă̍l�@�́A���̒n�ɏZ�މ�X�����ɑ傢��������b��ł���B����̑O�����ƍŏI��̓��{���̍���]�ڂ����Ē����܂����B�ʐ^�́A���R�_�Y���H�����̓��{���u���i�٣�ł��B
�@
�y�ږ��ɂ���Ď������܂ꂽ���{�H�́A����̗���ƂƂ��ɍL�����Ă����B������{�H�́A�t�����X�����Ɏ������������Ƃ��ẴX�e�[�^�X���l�����A������ݖ����u���W���l�̎p�́A���������̂ł͂Ȃ��Ȃ����B�Ɠ����ɁA���̍L�������t�����e�B�A�ɂ́A���܂��܂ȐH���߂���ږ��j���B����Ă���B����ȍl������A�L�҂��ꂼ�ꂪ�H�ށE������I�сA�Ǝ��̎��_�Ň��H�̈ږ��j�������A���T��l���ÂЉ�Ă����B�����A�ڂƂ��������܂Ȕ̏�ɍڂ����A�L�҂��ꂼ��̇�����������������Ăق����B�z
|
|
|
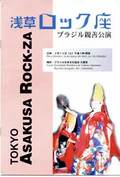 |
�u�����邱�ƁA�����邱�Ɓv�̌㏑���u�����̉āv�_�R�@�T�m������̊�e�B
��N3���ɐ��b�N���u���W���e�P�����ɗՎ����o�ƂƂ��ē��s���ꂽ�h�N���^���[��ƁA�_�R�@�T�m�����莞�Ɋ��ւ���Ă���܂����A���L�̂��ւ���܂����B�u�����邱�ƁA�����邱�Ɓv�̌㏑���ɏ����ꂽ�u�����̉āv�ł��B9�����ɏ㈲�����\��ł����ꑫ��Ɍf�ڂ����ĖႤ���ɂȂ�܂����B�o�ł������̖{�̕\�����f�ڗ\��ł�������܂ł́A��N�̐��b�N���̃u���W���e�P�����̃v���O�������f�ڂ��Ēu���܂��B�@
�u�ӉĂƂ͂����������������܂��B���������߂����ł����B
�^�Ẳ_�����グ�Ȃ���A����ȕ��͂������܂����B
�X�����A�҂�����㈲�����u�����邱�ƁA�����邱�Ɓv�Ƃ����A�����V����
�j�łɘA�ڂ��������l�����̃��|���^�[�W�����܂Ƃ߂���i�̌㏑���̂��߂�
���͂ł��B�v�@2002�N9��2��
|
|
|
 |
�ۍg�u���W����Ђ�5�N�ԋΖ����ꂽ����@ᩈꂳ��̊�e���B
���䂳��Ƃ͊ۍg�����Ɍ�ꏏ�Ɏd���������Ē������Â����Ԃł��B�����ۍg�u���W����Ђ�ގЂ���95�N�̑O�̔N�Ɋۍg���{�Ђł�����Ĉȗ��ł����A7�����ɂ��d���Ń|���g�A���O���܂ŏo�����Ă�����ӐH�������ꏏ���Ȃ���̂̃u���W���k�`�ɒ^��܂������A����u���W���Ζ������ƌ��݂̃u���W���̍��فA�f�����Ƃ��Ẵu���W���̌o�ωւ̓������Ѓ}���炵���ϓ_���炲�w�E�����Ă�����܂��B�u���W������̃G�d�A���h�N������27�Ƃ̎��A���̊u����������܂��B�ʐ^�́A7�����Ƀ|���g�A���O���ɗ���ꂽ���ɎB�������̂ł��B�^�̎�X�����̂����䂳��ł��B
|
|
|
 |
��n�ɖ����߂ā@�u���W���ږ��ƕ����ڎO�Y�̋O�Ձ@�y���ЏЉ�z
���̖���b���w�̑n�ݎҕ����ڎO�Y���i���a10�N�ɏ��߂Ė��ԃu���W���o�ώg�ߒc�c���Ƃ��ēn���j�ɕt���Ă̋O�Ղ��u��n�ɖ����߂āv�Ƒ肵�ď���@�琳����Ə㑺�@���b�q����(������b��w���̗���)�̋����Ő_�ːV�������o�ŃZ���^�[���2001�N6��11����P�Ŕ��s���Ă���A��N�̐_�˂ł̏�D�L�O��w��]�̑D�o�x�������̍ۂɎ�ނɏo�����Ă��������������Ƃ̂��Ƃōŋߑ����Ċ�z���܂����B�㑺����̂����h���Y�t����Ă��胁�[���A�h���X���������̂ŏ㑺����ɘA�����Ƃ蓯���́g�͂��߂Ɂh�̕����̓]�ڂ����肢����������L�̂��Ԏ����܂����B�ʐ^�́A�����̕\���ł��B
�w�u��n�ɖ����߂āv�ǂ�ł��������������ł��B
����搶�ƃu���W���ɂ��܂���܂��āA���炽�߂ĕ�������ɂƂ�A�Ȃ��A���̒n�Ȃ̂��������܂����B
�s��Ȗ����Ő푈������c�O�ł����B���B�ږ��Ƃ̍�����j�̒��ŏo�����������ł��B
�����ł��Љ�������̂́A���ꂵ���ł��B��������̕��ɓǂ�ł�����������K���ł��B�@�@�㑺���b�q�x
|
|
|
 |
�R�`�A�N�ڏZ�l�\���N�L�O���@�y�R�`�A�N�A�����c��s�z
�P�X�T�T�N�X���P�T���R�`�A�N��P���P�P�O�X�������߂肩�ۂŃT���g�X�ɓ��������̌㑫�|���P�R�N�ԂT�Q�q�C�œs���Q�T�O�W���̃R�`�A�N���u���W���ɑ��荞�B�Y�ƊJ���N���̂U�Q�U���A�H�ƈږ��A�͍s��̒c�̂ɂ�鑗�荞�݂̒��ł͐����I�ɂ����̌�̃u���W���Љ�ɂ�����蒅�A����́A�_���g�c�ł���A�P�X�X�T�N�Ɏl�\���N���}���R�`�A�N�A�����c���ÂŎ��Ԓ����A�L�O�����s�A�L�O�j�T�̂R���Ƃ��v��A�������Ă���B�L�O���̊��������Ƃ��ăR�`�A�N�A�����c��@������́y�o���V���Ɋ撣�낤�z��]�ڂ��Ēu���܂��B�R�`�A�N�Ăъ̕�̂ł��������čő�̂P�W�O�O�O�l�̑g������i������̃R�`�A�Y�Ƒg���́A�o�ϔj�]�𗈂����P�X�X�S�N�X���Ɏ�����U�ɒǂ����܂�Ă����̂�S�������R�`�A�N�A�����c��̍���̊��������g�������߃u���W�����n�Љ�Ŋ��҂���Ă���B���邺�Ȋۑ�P�Q���q�ł��R�`�A�N��Q����P�V�Ƃ��ĂS�O�N�ՂɎQ�����ꂽ�����߂P�V�����������Ă���S�����A�����Ă���܂����A���݂��R�`�A�N�Ƃ��Ċ���Ă���F����̏����������ׂĂ��܂��B�ʐ^�͂S�O���N�L�O���̕\���ł��B
|
|
|
 |
�����@���v�@�D�� �́y�L���v�e��SATO�̍q�C�����z�Ƀ����N���ĖႢ�܂����B
�y�L���v�e��SATO�̍q�C�����z�̃����N�W�q�����܂����B�����[��HP���f�ڂ���Ă��蔼�������玟�ƖK�₳���Ē����܂����B�y�����ĊC�̌������ɐ��E������܂��B�z(AROUND�@the�@WORLD)�̃J�e�S���[�Ɂw�������̂S�O�N!!�xHP�������N���Ē����L�������܂��B�C�̍D���Ȑl�����ɂ��邺�ȂȊۂƂ��邺�Ȋۂ��^���ڏZ�҂̐����l��FLW������Ί���������ł��B
���ӂ̔O�����߂ā@OBRIGADO�@CAPITAO�@SATO!!
�����D���Ƃ̌o�܂́A�ʐM���i�f���Łj�Ɍf�ڂ���Ă���܂����A�����D���̏����݂����L�ɏЉ�Ēu���܂��B��������ɐG��ĘA��������Ƃ̎��A�y���݂ɂ��Ă���܂��B
�ʐ^�́A�����D���̃��C��HP�̂s�nP�y�[�W�ɂ���A���X�J�ŎB��ꂽ���̂�]�ڂ����ĖႢ�܂����B�@
|
|
|