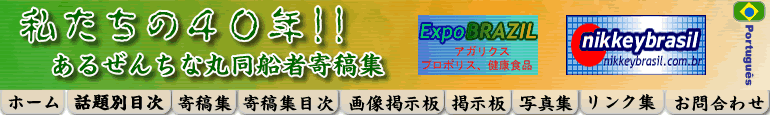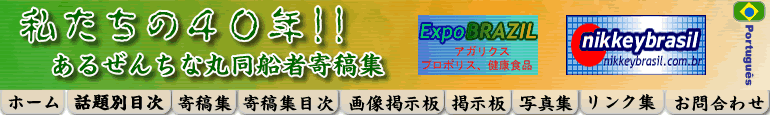|
首相官邸 小泉内閣メールマガジン〔ご意見募集〕欄宛て。
ポルトアレグレ総領事館廃止については、『私達の40年!!』HPでは一環して反対の立場を取りつづけていましたが、本日首相官邸 小泉内閣メールマガジン〔ご意見募集〕欄宛てに下記の公開意見書を小泉首相宛てに送りました。どのような対応があり、一HPの公開意見書が役に立つのかどうか?ポルトアレグレ総領事館廃止が現実になるとしても少なくとも我々が納得する「情報の公開と説明責任」は今後も追及して行きたいと思います。本件に関する皆さんのご意見等を掲示板にでも書き込んで頂けると幸いです。写真は同HPに掲載されている小泉首相の写真です。IT時代の便利さは格別ですね。
(追記)10月10日付けで内閣官房 官邸メール担当から小泉総理大臣あてのメールが届いたとの返事がありましたので本文の下段に掲載して置きます。
|
|
|
 |
「ブラジルと日本人」 故斎藤広志先生著 【書籍紹介】
サイマル出版会の倒産により絶版となってしまっている名著3部作が手元に残っているがブラジルの日系コロニア、ぬり絵社会と白紙社会、移民資料館づくり、日本人とブラジル人、フェジョアーダとお茶漬け、青春の日々、懐かしの人びと等どの章を開いても斎藤先生とブラジルが飛び込んで来ます。巻頭に「斎藤先生と私」という作家開高 健の巻頭言が掲載されているのでこれを本文で紹介しておきます。「斎藤先生は、背骨が1本、いや2本くらい通っているほどの剛気があった。友だちとして、あるいは師匠として、最高の人物であった。」写真は本書の表紙です。
斎藤先生の思い出−あとがきに代えて現日伯交流協会会長(当時日本ブラジル青少年交流協会事務局長)の玉井義臣さんの書かれた部分からお借りすると『先生が亡くなられた年の暮、私は交通遺児高校生の海外研修でブラジルを訪れ、先生のお墓参りをし、お宅の書斎で夫人から次のような話をうかがった。「両親がガンで死んでいるので気がついてはいたと思いますが、とうとう最後まで家族にはガンということばは口にしませんでした。しかし、夜など頭の髪をかきむしって、オレにはしなければならない仕事が残っている、と男泣きに泣くのを見るのは本当に辛かったです」と。また、医師に「もう二年、生かしてほしい」と言われたという話、死ぬ直前に強い希望で取り寄せた草野心平の「茫々半世紀」を家人に読ませ、満足げに聴きいっておられたという話など、聞いていて胸が痛んだ』
|
|
|
 |
来た道 行く道 移住助監督上園義房さんの新聞連載より(3)
上園助監督の宮崎日日新聞に連載は101回まで続いておりますが、横浜、神戸からベレン、サルバドール、リオそしてサントスまでの私達の人生の一部、貴重な時間を共有した者には忘れられない10回のエピソードを書き残しておいて下さった上園兄に深く感謝の念を捧げます。字数の関係でこの船内生活に加えて96年に来伯された時の「三カ国訪問終える 勤務地の発展に驚き」及び99年にアマゾン地域の移住七〇周年記念式典で勲章「日伯功労章」を受賞するために来伯された時の「ラジオ体操 南米各地でも流行」の2回を付け加えておきます。写真は96年に来伯された時にサンパウロで撮られたブラジル裏千家代表 林宋慶教授を挟んで右側は、同船者のブラジルDEC園田社長です。
|
|
|
 |
【当州は、日本国総領事館を失うかも知れない】 10月4日付けZERO HORA紙記事より
ポルトアレグレの最大発行部数を誇るゼロ・オーラ紙は、2002年10月4日(金)付けでANDREI NETTO記者の署名記事として総領事館前で撮った牧領事の写真入りで「当州は、日本国総領事館を失うかも知れない」「1959年に開設された総領事館の存続を目指し地元在留邦人が署名運動を展開中」との見出しで半面を使って報道している。小さな開設欄には、「米国、フランス等は既に閉鎖」との見出しで既に六年前に当州は経費節減の為にアメリカ総領事館が閉鎖された。ポルトアレグレのアメリカ領事館は、1996年7月19日に時のMelvyn Levitskyアメリカ大使により閉鎖された。これはアメリカの18在外公館閉鎖の一環としての処置であった。ポルトアレグレの総領事館は当州とサンタカタリーナ州を管轄としており閉鎖前の1996年6月には6800通の査証を発行していた。ポルトアレグレ総領事館閉鎖により南2州の査証申請者は、直接面接が必要な場合サンパウロまで出かける不便を強いられる事になった。1996年より以前に既に正規外交団によるフランス総領事館は閉鎖されたがその後も民間の名誉領事を任命査証業務等は継続している。
写真はZERO HORA紙の記事をそのまま掲載し、その翻訳を本文に記しておきます。
|
|
|
 |
新版「新しいブラジル」 故斎藤広志先生著 【書籍紹介】
今はないサイマル出版会を通じて出版した斎藤先生の3部作の新版「新しいブラジル」です。第1章 グレート・カントリーへの道―イメージ、第2章 三つの文化と移民−歴史、第3章未開と文明の共存―社会、第4章 開かれた日常生活−生活、第5章 ブラジルのなかの日本人−日系人の内容は、第5章を除き1974年秋の初版のままで1983年9月に新版で第5章が書き加えられた。初版から数えると30年近くなるが今も新しいブラジルとしてそのまま生きている内容でこれは普遍的なブラジルに育ち、生き抜いて来られた斎藤先生の鋭い観察眼と暖かい人間性を基礎にした書き物であることから時代を超越した真実性を持って私たちに迫ってくる。
巻末に「斎藤先生と私」という日伯交流協会玉井義臣会長(当時交通遺児育英会専務理事)の追記が残っている。
(追記)斎藤先生は10月31日、直腸ガンのため、サンパウロで亡くなりました。享年64歳。81年暮れから4度手術され、私たちはこの日のくるのを一番恐れていました。最後の手術の際、医師に「仕事が残っている。もう2年、生かしてほしい」と言われたとのことである。仕事とは、『異文化のなかで50年』の執筆と、日伯青少年交流のことであったに違いない。藤村とともに、無念のご遺志の何ほどかでも継ぎたい。まず、遺稿『続・外国人になった日本人』(仮題)の上梓を実現したいと希っている。(1983年11月1日)
|
|
|
 |
トメアスー移住地の三宅昭子(旧性佐藤)さんからのお便り。
1月に北伯アマゾンの河口べレンで下船した同船者31名の動向を訪ねての旅でほぼ40年振りに胡椒の里トメアスー移住地を訪問しました。船内新聞の編集委員の一人として活躍された三宅昭子(旧姓佐藤)さんより8首の俳句と共に近況を知らせるお手紙を頂きました。原文のままタイプアップして置きます。
このお手紙は一度『私達の40年!!』HPに掲載しておりましたが、ご本人より一部書き換えたいので削除して欲しいとの依頼受け削除しておりました。今回新しく書き換えた文を郵送して呉れましたので再度タイプアップしたものです。
写真は、前回と同じトメアスー十字路から程近いご自宅の花の咲き乱れる庭で撮ったものです。
|
|
|
 |
【嬉しい便り】中村 實さんからの寄稿。
多摩市にお住まいの中村 實さんからノーベル賞のダブル受賞の快挙を伝えるお便りを頂きました。朝日新聞の報道と共に掲載して置きます。
小柴さん、田中さんと首相は「3兄弟」? 一緒に昼食
日本で初めてノーベル賞の「アベック受賞」となった島津製作所ライフサイエンス研究所の田中耕一さん(43)=ノーベル化学賞=と東大名誉教授の小柴昌俊さん(76)=同物理学賞=の2人が11日、小泉首相(60)の招きで首相官邸を訪れた。
4階の特別応接室で2人と対面した小泉首相は、握手を交わして2人の受賞を祝福。記念撮影で2人にはさまれて首相は「3兄弟みたいだ。年代的にも3兄弟だね」と上機嫌だったが、田中さんは「そんな恐れ多い」と照れ笑い。
ノーベル賞を受賞する小柴昌俊・東大名誉教授(左)と田中耕一・島津製作所主任は小泉首相から握手を求められ記念写真に納まった=11日午後0時19分、首相官邸
|
|
|
 |
佐藤揚明さん(8期生、秋田県出身)が亡くなりました。
南米産業開発青年体の8期生で同船者の佐藤揚明さんが志半ば62歳を迎える寸前に交通事故で急逝しました。寄稿集136番【悲報】産業開発青年隊 佐藤揚明さん急逝!!でもお知らせしている通りですが、この度同期生で同船者の小島徳さんが書かれた僚友佐藤さんの死を悼む文が寄せられましたので掲載しておきます。佐藤農場の航空写真は、写真集にも別途掲載して置きました。
|
|
|