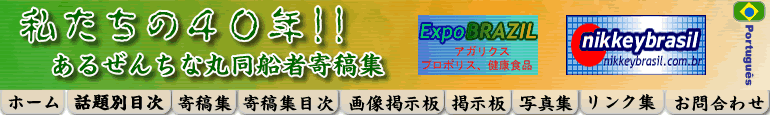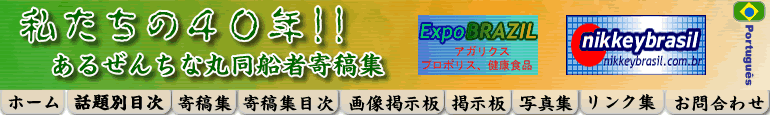|
石川達三と『蒼氓』について。【大地に夢求めて】付記3より転載。
第1回の芥川賞受賞作品でブラジル移民を主題とした余りにも有名な石川達三の『蒼氓』に付いて【大地に夢求めて】(寄稿集14ページ143項に書籍紹介として掲載)の付記3として掲題のコメントが載っている。著者の小川守正さんの『蒼氓』に書かれた世界とその影響による移民=棄民が定着し一人歩きしがちであるが決して「移民=棄民では断じてない」との結論に賛意を表する者の一人である。“『蒼氓』はあくまでも石川達三の作品であり、そこに盛られているのは彼の心であって、移住者自身の心ではない。彼はブラジルの地は踏んでいるが、本当の移民ではなく悩める文学青年の逃避行であったのだから、当然のことでであろう。”文学作品と移民の実生活を切り離しての論法には、喝采を贈りたい。少し長くなりますが全文を転載して置きます。写真は1935年(昭和10年10月)に改造社より出版された初版の表紙です。
|
|
|
 |
【40年目の出合い】 三宅昭子さんのエッセイと俳句。
北伯アマゾンの胡椒の村トメアスーに住んでおられる三宅昭子(旧性佐藤昭子)さんよりお便りを頂きました。三宅さんは船内ニュース班の一員として活躍され文章を書くのが大好きとの事で現在はトメアスーの移住地で日本語を先生をされております。俳句を嗜まれ俳文学127号に上掲の「40年目の出合い」と題するエッセイを寄せておりそのコピーを送ってくれました。寄稿集1ページの第6項にある「小雨のベレンで下船された同船者を訪ねての旅」に出ている写真の日の丸の旗への寄せ書きにその主人?に当たる私が日章旗との40年振りの面会を果たした事実に付いてどうして佐藤家にこの日章旗が保存されておりトメアスー文化会館の移民資料館のメイン展示場に陳列されているのかを考察しており私自身も1962年2月5日の日付けで壮行会を開いて呉れた懐かしい友人の名前と寄せ書きに暫し見入る感激の一瞬でした。「持ち主が表われ持ち帰りたいと云い出す事を恐れていた」とトメアスー文化協会穎川会長の弁ですが、歴史の一部として大事に保管、陳列されている日の丸の旗を見て良かったと感謝こそすれ所有権?を主張する積りは毛頭なく今後とも宜しくとお願いして帰ってきました。アングルが違うもう一枚の写真をここでも掲載して置きます。
|
|
|
 |
在ポルトアレグレ日本国総領事館廃止報道に関して
在留邦人保護を主目的にブラジルには、サンパウロ、リオ、ベレン、ポルトアレグレ、レシフェ-、クリチーバ、マナオスと7総領事館に加え首都ブラジリアに大使館があります。1960年に開設されたポルトアレグレ総領事館は、42年に渡り南2州の在留邦人保護、日本文化の紹介、近年とみに重要性をますメルコスール域内主要都市としてのポルトアレグレにおける域内及び日本との経済交流等積極的な活動を展開して来ているポルトアレグレ総領事館が存続の危機を迎えている。事の発端は、外相の私的懇談会『外務省を変える会』からの提言を受けて必要性の低下した公館を廃止し、アジア地域を増強するという基本方針が出されその廃止公館の中にポルトアレグレが入っているとの朝日新聞の報道がインタネットを通じて世界を駆け巡った。我々ブラジル南部ポルトアレグレに住む者に取っては“寝耳に水”の驚きでありこのまま手を拱いて傍観する事の出来ない重要事項と捉え地元日系指導機関である【南日伯援護協会】、南伯日本商工会議所、日系クラブ等の団体はもとより、一人一人の個人としても容認できるものでないとの見解から署名嘆願運動を展開している。不祥事件が相次いだ外務省内で『外務省を変える会』等を通じて開かれた外務省、国民が納得できる外務省を標榜し模索している事は有難い事であるが、膨らみ過ぎた?在外公館数の制限、アジア重点主義等の基本方針のもとに在外公館の見直しも必要とは思うが在留邦人が多数存在する公館の廃止等に付いては十分なる現地調査、地元民の納得が得られる形で実施するべきであり川口外務大臣にもこの点を分かって貰いたいと望むものであり、署名運動等の動きも充分に考慮して判断して貰いたいと願う次第です。写真は、9月11日に撮った現在のポルトアレグレ総領事館(日本国政府の所有で治外法権が実施される我々日本人の所有財産)です。
|
|
|
 |
『神戸じいじ』さんのW杯関連コメント
『私達の40年!!』HPでもサッカー関係のニュース、特に日韓共同で開催されたW杯に付いては、色々掲載しておりますが、神戸の15千回近いアクセスを誇る『神戸じいじ』さんのHP『神戸じいじ』のひとりごとの欄にW杯について「W杯の開会」と「W杯一次リーグ突破」と題して2度コメントをしておられます。サッカーを冷静に見ておられる日本人の代表として掲載させて頂きました。写真は同HPの自己紹介の欄から転用させて頂いたお孫さんとのものです。同HPのURLは、www2.sdia.or.jp/~kouzai/ です。
『私達の40年!!』HPにはサッカー関連記事として、寄稿集目次86項、87項、90項、91項、95項、101項、102項、114項、125項等にサッカーに付いての文が掲載されております。一緒にお読みください。
|
|
|
 |
『第四十三回南日伯援護協会主催家族慰安敬老会、演芸会』開催。
平成14年9月7日(土)に『第四十三回南日伯援護協会主催家族慰安敬老会、演芸会』が地元ポルトアレグレのサグラーダ・ファミリアの大講堂で500名以上の日系人を集めて盛大に行われました。午前9時の開会式から始まり演芸会午前の部、東西歌合戦第1部に引き続き恒例の敬老会では70才以上の高齢者(年々数が増えコロニアは確実に高齢化社会に突入しつつある)に対し記念品贈呈とお昼のお弁当が手渡された。来賓挨拶では津嶋冠治ポルトアレグレ総領事と当地カトリック大学老年医学研究所長森口幸雄博士が世界一長寿国日本にブラジルに移住して来た皆さんもできるだけ近づいて欲しいと予防医学としての成人病予防の検査と巡回診療への参加を呼びかけられた。写真は第四三回南日伯援護協会主催家族慰安敬老会で挨拶をしてたおられる森口幸雄博士。本文には、敬老会で主催者としての南日伯援護協会刀禰康弘会長の挨拶文を掲載して置きます。
今年の敬老会ではポルトアレグレ総領事館の閉鎖のニュースに多くの参加者が不安と不満の意向を表明、家族揃って『ポルトアレグレ総領事館廃止反対署名』に競って署名し持ち帰って賛同者を募り署名運動を盛り上げたいと積極的姿勢を示していた。
|
|
|
 |
『私達の40年!!』HP旧トップページの保存。
平成14年3月中旬に『私達の40年!!』HPを立上げ試験的に公開、4月より一般公開しました。アクセス数は、同船者の皆さんとその関係者に限られていた7月末までは月間300件―350件(1日10件前後)でしたが8月から日本の栗本克彦さん、桐井加米彦さん、香西仁さん等のシニアー名門HPとの連携とご支援により日本の皆さんにも見て頂けるルート作りが出来飛躍的にアクセス数が増え8月に2000件、9月16日に3000件のアクセスを達成しました。現在1日平均40件のアクセスがあり年末、あるいは来年の公開1年目にはどれ位まで伸びているか楽しみです。3000件達成を期して『私達の40年!!』HPのトップページの内容を更新することにしました。TOP PAGEだけでも字のサイズを大きくして読みやすくすること、寄稿集の目次を作り直ぐに読みたい項目に飛べるようにする事、通信欄を日本並に掲示板と表示し直す事、これまでの正会員、準会員と言った区別、または登録手続きを省き総ての人に垣根なく参加して頂き書き込み、寄稿がし易くします。
TOP PAGEの記載事項は、6ヶ月経過した現在、『私達の40年!!』HPに相応しいものに書き換えるにあたり旧トップページをここに掲載保存しておく次第です。
写真は、香西仁さんより送って頂いたあるぜんちな丸の三菱造船所内にある展示室に展示されている展示ケースです。写真集にあるぜんちな丸だけを掲載しております。
|
|
|
 |
海外7公館廃止へ 7公館新設 外務省、初の見直し 【8月21日付け朝日新聞朝刊一面の記事】
既に『私達の40年!!』HPでも取り上げている14ページ149項【在ポルトアレグレ日本国総領事館廃止報道に関して】及び15ページ151項【第四三回南日伯援護協会主催家族敬老会、演芸会開催】に記載しているポルトアレグレ総領事館の05年度廃止決定との報道は、当地のみならずブラジル全土でその閉鎖の正当性が論議されており、単に語呂合わせで7公館廃止、7公館新設(最後の新設場所はいまだ決めてもいない)は、『私達の40年!!』HPに書き込まれたかずさんの『不祥事から目をそらすための便法でしょう。』との御指摘が説得力を持つ措置ではないかと思う。この朝日新聞の報道が単なる事実の羅列に終わって仕舞っているのであれば「社会の木鐸」と云われる大朝日新聞は、その報道内容に責任を持っているのでしょうか?統廃合される在外公館の一つ一つの歴史と公平な重要性、その背景等に付いても言及する必要があると思います。日本人の観光客が増加したから新設し40年近く在留邦人を世話して来たが必要性が低下したのでこれ以上は自立しろというのが戦略的な配置、外務省改革なのでしょうか。私たち在留邦人は、この原案に対して最後までその存続を叫び続けて行きたいと思います。前述のかずさんのコメント『外務省による経費節約のための領事館閉鎖は、米デンバーのような新設、不急不要な領事館を閉鎖し,南米のように在留邦人が多く、出稼ぎ、ビザの発給などのため、ぜひ必要な領事館は閉鎖すべきではないと思います。』が良識ではないかと思います。皆さん応援して下さい。
写真は、8月21日付け朝日新聞朝刊第1面の切抜きです。
|
|
|
 |
アルゼンチンに入られた40名の同船者の動向を知らせて貰いました。
あるぜんちな丸第12次航の同船者でアルゼンチンに移住された単身の田上英明さん(1941年生まれ=現在もブエノスに在住)とガルアッペス移住地に入植された9家族39名の消息が掴めず殆ど白紙の状態で気になっておりました。何度かブエノスのJICA移住問題担当官宛てにメールを出し様子を教えて欲しいと頼んで見たのですが返事を頂けないままになっておりました。栗本克彦さんのHPの書き込み欄にブエノス在住の林正明さんの名前を見つけ8月6日付けでお願いを掲載させて頂いた所、翌7日にはお返事を頂きガルアッペスの近くのオベラの町で花弁栽培、花屋さんを経営しておられ移住地で日本語の先生をしておられる永江久利さんを電話番号と共に紹介頂きやっと現地と連絡が付きました。9家族の内2家族が現在もガルアッペスに住んでおられるとの事で残りの方は殆どがブエノスに移り、一部は日本に帰国されたとの事です。永江さんから送って頂いた動向浮ノよると確定している8名の死亡者がおられ帰国された方等でその後の消息が掴めていない同船者等を加えると25%以上が故人となられている様で時の流れを感じます。写真は2004年8月に同移住地を訪問し現在も営農を続けておられる多田直広さんご夫妻と高松康三さんとご一緒に撮らせて頂いたものです。
|
|
|