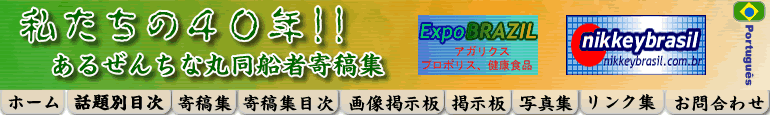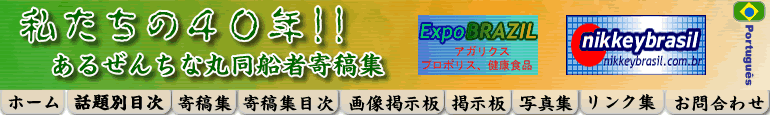|
画像掲示板の書込み一部永久保存開始。(6)
画像掲示板の書込み保存第6回目です。使用ソフトの関係で1回に1万語までですのでそれ程沢山は、保存できません。掲示板より写真を見ながらもう1年半も前の書込みを読み直して見る作業は、結構懐かしく楽しいものです。5月30日の画像掲示板のアクセス数が18814回で書込数が1224回ですので15回のアクセスに1回の書込みという数字が出てきます。『私たちの40年!!』HPの画像掲示板は、内容が管理人の書込み(寄稿集のPRとか個人的な書込み)が多い性かその内容が偏っている為か気軽な書込みが少ないようで残念ですが参加する書込み掲示板よりお知らせを見る掲示板になっている様です。どうすればもっと参加し易い掲示板になるのか研究して見る必要がありそうですが、それでも大いに役立ち喜ばれているのではないかと思います。
写真は、神戸在住の神戸じいじさん事、香西仁さんの年賀状のダイサギの雄大な飛翔をお借りしました。有難う御座います。
|
|
|
 |
画像掲示板の書込み一部永久保存開始。(7)
画像掲示板に書込みをして下さった方が何人位居られるか、数えて見るのも楽しみですが、バーチャル座談会の日本側主要メンバの神戸じいじさん,MASAYOさん、桐井さんのご3人には、各HPにこのバーチャル座談会の紹介コーナを設けて頂いております。その他にも日本の皆さんのHPに『私たちの40年!!』HPをリンクして頂いておりこれが目に見えない方達からのアクセスに繋がっている様で今月は、開設2周年の節目の月でしたが、月間4000件台をキープしてきたアクセスが始めて月間5000件に到達しました。一日平均168件のアクセスと初期の段階では考えられなかった事で何時頃からかブラジル国内よりのアクセスより日本からのアクセスが中心になり南米諸国(同船者がいるアルゼンチン、パラグアイ、ボリビアが中心)アジア、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニアと世界中からのアクセスが記録されており今月はウズベキスタンという旧ロシア連邦の国からのアクセスもありルーマニア他、東欧諸国からのアクセスも見られます。これらの国々からアクセスされた方の書込みが出てくると嬉しいのですが。。。
写真は、何時も暖かい書込みを寄せて下さる大分にお住みの桐井加米彦さんから貼り付けて頂いた『初春の別府市扇山』の写真をお借りしました。有難うございます。
|
|
|
 |
【企業誘致と日系人就労への試み】 元JETROサンパウロ所長湯沢三郎さんよりの寄稿。
JETROのサンパウロ所長をしておられた湯沢三郎さんから任期中に手掛けられた【香港テクノセンター】(石井次郎代表幹事=当時)のブラジル版育成事業を推進されブラジル各地で石井さんの講演とブラジル版テクノセンター設置支援を頂き現在でもその構想は、モジダス・クルゼス市、サンジョゼドスカンポス市、ポルトアレグレ市、ゴイヤニア市等の地元の有志に引き継がれております。
今回、当時の事情を湯沢三郎さんから寄稿頂きましたが、奇しくも湯沢さんとは早稲田の政経入学が同じ年だとの事でブラジル在任中には大変ご懇意にして頂き、同じ夢を共有させて頂き、その後中米のエルサルバドールの大使として在勤して居られる時に香港テクノセンターの石井次郎さんと私と女房も同伴でメキシコ経由エルサルバドールまで陣中見舞いに出かけ旧交を温めましたが、それ以来お会いする機会が有りませんが、現在はJETROを離れもっぱら海外体験を青少年に語り継ぐNPOに携わっておられ、日々の生活を楽しんで居られるとの事ですので次回訪日時には、是非また一献傾けたいと念願しております。有難う御座いました。
|
|
|
 |
【産業開発青年隊 パラナ訓練所・元所長 石井延兼 レクイエム】牧 晃一郎 さんの寄稿
あるぜんちな丸第12次航には、建設省派遣の産業開発青年隊員が合計33名が乗船しておりました。既に5人の仲間が亡くなられておりますが、今も各地で元気に活躍しておられます。その内の一人牧 晃一郎さんは、南米産業開発隊協会の会長にこの4月に就任しておられます。1956年6月9日にサントスに到着したに第一期生18名から合計326名の産業開発青年が来伯、帰国者もいますが現在でも200数拾名がブラジルにおられ大きな団体としてその結束を誇っています。新しい会長としての牧さんの今後の青年隊50周年へのビジョン等をパラナ訓練所長をしておられた石井延兼さんへのレクイエムとしてパラナ訓練所時代の思い出を通じて語っておられます。原稿は、随分前に頂いていたのですが、デジタル化(タイプアップ)が出来ずにそのままになっていましたが、大阪に住む妹の阪口多加代にやつと叩いて貰いました。
写真は、今週サンパウロに出向いた時に昼食を共にしながら産業開発青年隊の今後への抱負等をお聞きしながら撮らせて頂いた近影です。
|
|
|
 |
【46年前の初めてのブラジル出張】 近畿車輛辻課長(当時)のブラジル体験記(書き下ろし特別寄稿)
インターネットを通じてお知り合いになった元近畿車輛に勤務しておられた辻 重雄さんより貴重な寄稿を送って頂きました。私たちより4年も前にブラジルにソロカバ線の車両引渡しに立ち会う為にブラジルに来られたとの事で、当時の様子を克明に記録、瑞々しい表現で再現して下さっております。2度目の来伯時1962年にはポルトアレグレにも立ち寄られたとの事で(ブエノスからリオに向う途中ポルトアレグレに不時着?)少し変色した当時の写真も提供頂いており画像掲示板にご披露する予定です。
辻さんは、現在宝塚にお住いで、1921年生れの83歳、6人のお子さんにお孫さんと大家族を形成、お元気に過しておられる様子、辻さんのHPもリンクさせて頂きました。インターネットを通じ大きな繋がりが見られ嬉しい限りです。写真は、辻さんのHPからお借りした辻さんの老いて益々お元気そうな写真です。
|
|
|
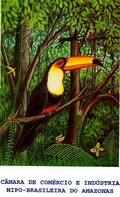 |
ルーラ大統領の訪中随行員として中国に出向かれたマナオスの山岸照明さんとサンパウロの工藤章さんの報告。
今回のルーラ大統領の超大型訪中ミッションに随員としてマナオスフリーゾン(ZFM)代表の一人としてアマゾナス日系商工会議所会頭の山岸照明さんとサンパウロの前ブラジル日本商工会議所会頭の工藤章さんのお二人が参加しておられbatepapoのMLにその経験を報告しておられます。内輪の情報であり公表するに値するかどうか疑問な点もあるとのコメントと共に『私たちの40年!!』HPへの転載を快諾頂きましたのでご紹介させて頂きます。
ブラジルと中国の二大国の接近、日本上空を飛び越しての今回の大型ミッションのもたらすものは何を意味するのでしょうか。一部閣僚、州知事等が帰路日本にも立ち寄ったようですが、実際問題として今、日本がブラジルに何を提供できるのか、今回の訪中のようなインパクトを持つ日伯関係の確立は、望むべくもなく『蚊帳の外』の疎外感を感じざるを得ないのが事実で『嬉しくもあり寂しくもある』複雑な気持です。ブラジル日本移民100年を迎える我々移住者は、どのように対応して行けばよいのかポルトアレグレ総領事館の閉鎖問題等と共に考えさせられる所です。
写真は、山岸さんから旅行中の写真を送って頂く事になっていますが、一先ずアマゾナス日系商工会議の会報の表紙の写真を使わせて頂きました。
|
|
|
 |
日本ブラジル移住者協会 移民100周年記念事業草案 徳力啓三
私の所属している夢・ベテランのMLのメンバーは、元日本学生海外移住連盟のOBを中心とした 老いた?今も夢を追い掛ける者たちの集まりですが、メンバーの一人、徳力啓三さん(三重大学卒)が移民100周年記念事業として日本ブラジル移住者協会を母体として大きな夢をぶち上げています。熟年パワー炸裂の文化の町 「夢ベテランの里」建設案は、我々ブラジル戦後移住者一人一人が真剣に考え取組んで行く価値のあるプロジェクトと云えます。『私たちの40年!!』HPの底辺に流れる基本理念、681名の同船者の定着の過程、現在、未来をどのように戦後ブラジル移民史の中で残して行けるかを追求する姿勢で取組んでいますが、徳力さんの移住者を中心とした村作りの構想実現の道と大きく交差する面が大きく是非一緒になって同じ思いを追い掛けて見たいと思います。徳力さんへの支援、私達自身の努力、この欄でもその成行をフォロウして行きたいと思います。
昨年7月にサンパウロで行われた戦後移住者50周年記念式典で始めてお会いした時に撮らせて頂いた写真です。
|
|
|
 |
『回り道をした男たち』三重大学農学部南米三翠同窓会史 徳力啓三さん寄贈
日本学生海外移住連盟のメンバー校の一つ三重大学出身者で形成する三翠会の同窓会史が発行された。『回り道をした男たち』の一人徳力啓三さんより貴重な同窓史を送って頂き早速ページを繰っておりますが、徳力さんにお願いして彼の書いた【ブラジルに描く夢】だけでも全文ご紹介したく思います。徳力さんは、1941年に三重県は、松坂城下の商家の次男坊として生れ小学校3年生の頃からブラジル行きを発言していたとの事で長じて松坂工業高校の機械科から三重大学農学部に現役で入学、1964年に学移連の派遣団第5回生として仲間11人と1年間研修、1995年10月三重大卒業、1996年4月にブラジルに移住。その後のブラジルでの生活、定着の過程、現在と未来への展望を自分史として克明に語る。是非皆さんにも読んで頂きたいと思います。
写真は、同窓会史の表紙をお借りしました。尚、ニッケイ新聞の6月12日(土)版にも記事として掲載されていましたのでお借りしました。
|
|
|